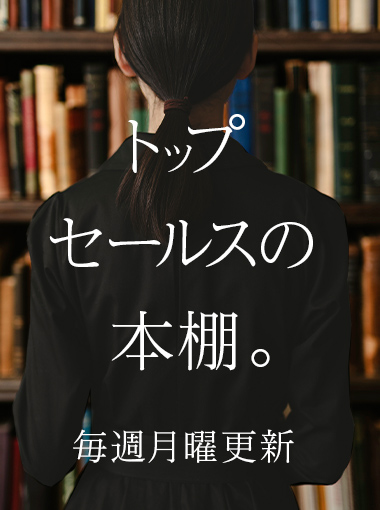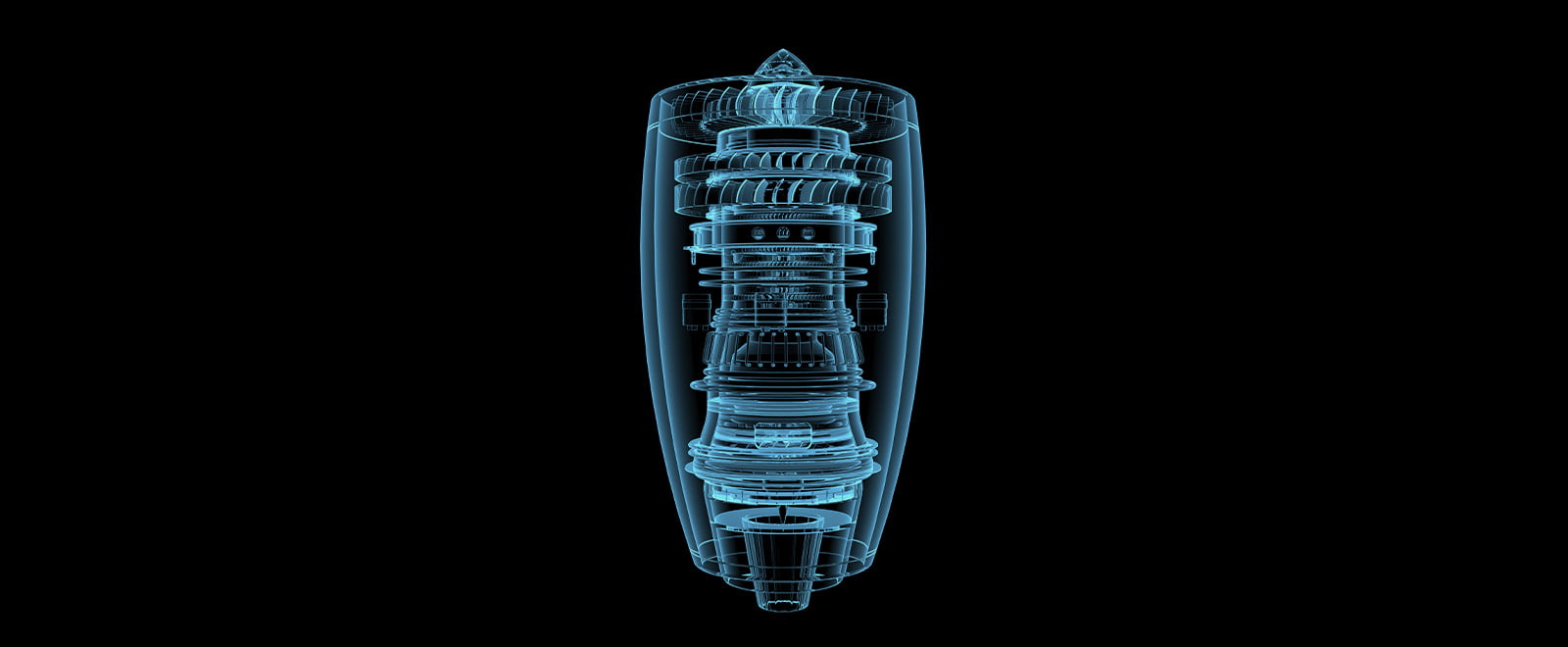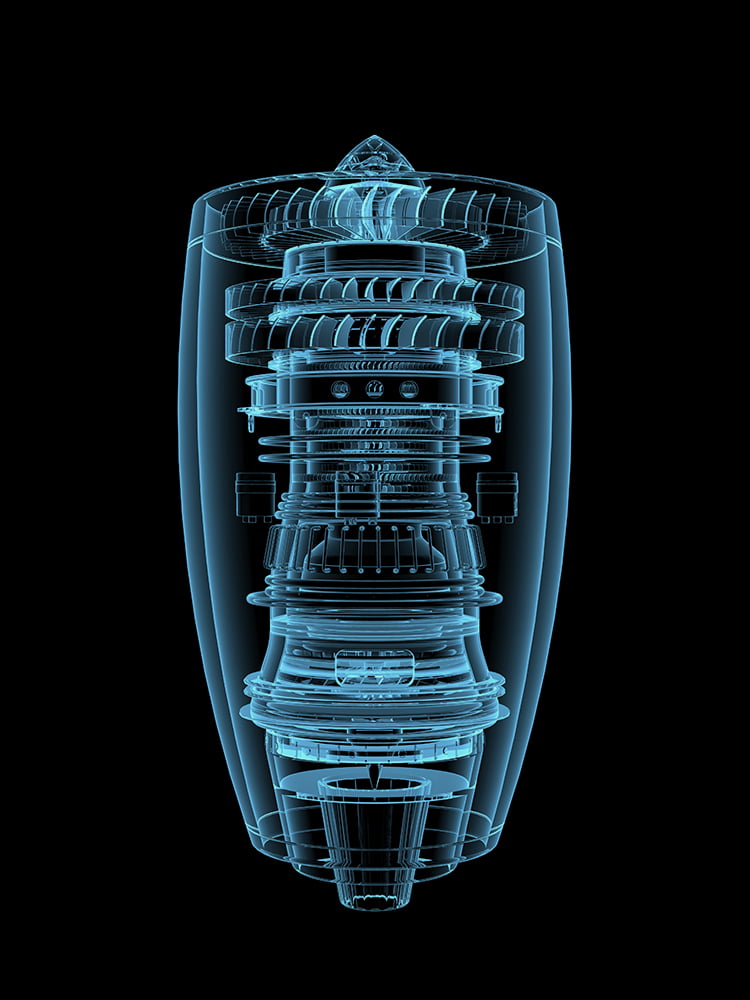経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術(小野 壮彦著 2022年 フォレスト出版社)~人材を見抜く極意~
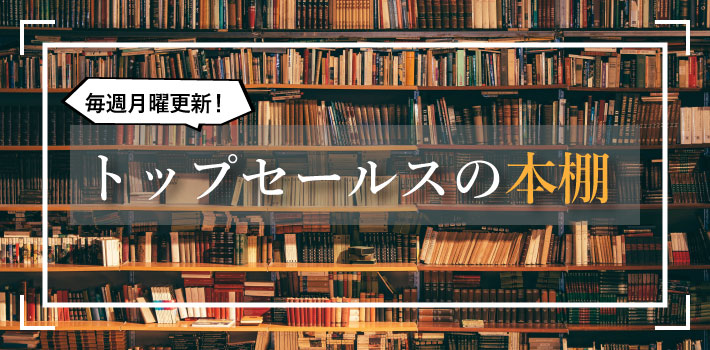
こんにちは。荻原です。
今回のトップセールスの本棚では、営業パーソンに限らず、あらゆるビジネスパーソンに役立つ一冊をご紹介します。
本日、インタビューに答えてくださったのは、アルヴァスデザインにてマネージャーとして活躍中の松下さんです。
松下さんが選ばれた書籍「人を選ぶ技術」は、人を見る目を養い、その本質を理解するための視点を提供してくれる一冊です。
書籍の中から得られた学びについて、詳しくお聞きしました。
目次
1. 「人を選ぶ技術」はどんな書籍?

荻原:本日は、よろしくお願いします。はじめに、松下さんのおすすめの一冊について簡単にご紹介お願いします。
松下:はい、今回私が選んだのは『人を選ぶ技術』という書籍です。グロービスキャピタルパートナーズディレクターの小野 壮彦さんが著者です。
この本は、人の本質をどのように見抜いていくかについて、人を階層で捉えながら解説しています。
荻原:非常に興味深いですね。
松下:はい。特に、人と接する機会が多い営業には、本書籍が役立つのではないかと思い選びました。
また、営業に限らず、ビジネスパーソンであれば必ず人と関わる場面がありますので、人の構造を理解しておくことは非常に有益だと感じています。
2. 「人を選ぶ技術」で印象に残った「四層構造モデル」

荻原:本書を読んで、特に印象に残ったポイントはどんなところでしょうか?
松下:最も印象的だったのは、人を「四層構造」で捉えるモデルです。
本書では人をビルのような構造に例えています。具体的には、地上に見える部分と地下に隠れている部分に分けて説明しています。この捉え方はとても分かりやすく、人を見極める際の新たな視点を与えてくれます。
まず、地上に出ている「1階」の部分が「経験・知識・スキル」です。これは、履歴書や面接、実績などから比較的簡単に確認できる“目に見える”部分です。しかし、この層だけで人を判断するのは表面的な評価に過ぎないというのが本書の主張です。
荻原:確かに、一般的には人は経歴や学歴などの分かりやすい部分で相手を判断してしまいがちですが、それはその人の本質であるとは言い切れないですよね。
松下:その通りです。次に「地下1階」となるのが「コンピテンシー」、つまりその人の行動特性です。表面的には見えにくいけれど、時々見え隠れする部分です。
本書では、特にリーダーに求められるコンピテンシーとして、
「成果志向」、「戦略志向」「変革志向」の3つを挙げています。
高い目標をやり切る力、長期的に物事を考える力、そして現状を打破する力、これらが日常的に姿勢としてあらわれることが大切だと感じました。
私自身も、自分の中にこの3つの要素があるか?と振り返るきっかけになりましたし、人と関わる際にも意識するようになりました。
荻原:なるほど、性格というより“行動に表れるその人らしさ”なんですね。 一緒に仕事をしていても、そのような姿勢って確かにふとした場面で見えてくる気がします。だからこそ、日常の中でじっくり見ていく視点が大切なのですね。では、次の階層についてもぜひ教えてください。
松下:はい。さらに深い「地下2階」には「ポテンシャル」があります。これは潜在能力、つまりその人の将来的な成長可能性を指します。

本書によると、このポテンシャルを構成する要素も四つあり、土台となるのが「好奇心」です。新しいことを学びたい、知りたいという意欲がポテンシャルの基盤になります。その上に「洞察力」「共感力」「弾力性」という三つの要素があるとされています。
特に興味深いのは、本書が「何ができるか」ではなく「何をすることにワクワクするか」、「エネルギーが湧くか」がポテンシャルを発揮できるポイントだと指摘している点です。つまり、単に能力があるだけでなく、その能力を発揮することに喜びを感じるかどうかが重要だということです。
荻原:確かに、やりたくないことには全力を注げませんよね。その「好奇心」がポテンシャルの土台というのは納得できます。
松下:そして最も深い「地下3階」に「ソース・オブ・エナジー」、つまりその人を突き動かす“エネルギーの源”があるとされています。これは「使命感(ミッション)」と「劣等感(コンプレックス)」の二つから構成されています。使命感は何かを守りたい、達成したいという強い意志、劣等感は自分の弱みを克服したいという強い欲求です。
例えば、成功している経営者や一流のスポーツ選手などを見ると、強い使命感や劣等感からエネルギーを得ていることが多いというのは良い例なのかもしれません。
その他にも「子どものためにより良い教育を提供したい」という使命感や、「自分の弱みを克服して成功したい」という劣等感が、人を突き動かす強力なエネルギー源になるとあります。
荻原:なるほど。成功している人の背景には、そういった強いエネルギー源があることが多いのですね。
松下:はい。重要なのは、この四層構造の中で、深層に行けば行くほど変わりにくいものだということです。「1階」の経験・知識・スキルは学習や訓練で比較的短期間で変化しますが、「地下3階」のエネルギー源は簡単には変わりません。
このモデルが示唆するのは、人を評価する際、表面的な経験やスキルだけを見るのではなく、その人の行動特性、ポテンシャル、そしてその人を突き動かすエネルギー源まで目を向けることの重要性です。
特に今の時代は、スキルの変化が早くなっています。だからこそ、どんな環境でも自ら学び、変化に対応できる「ポテンシャル」がより注目されているのだと思います。
荻原:深い考察ですね。人を見る視点が一気に広がる感じがします。
3. 「人を選ぶ技術」から学んだ実践的視点

荻原:この本から得た学びで、日々の仕事に何か変化はありましたか?
松下:大きく二つあります。まず一つ目は、「自分を知らなくては他人を見ることはできない」という気づきです。
本書には、私たちは皆バイアスを持っていて、自覚しているものもあれば全く気づいていないものもあると書かれています。人を評価する前に、まず自分自身の持つバイアスや無自覚な反応を見逃さないようにすることが大切だと学びました。
二つ目は、人と接する際に「この人の原動力は何だろう?」「ポテンシャルの源泉は何だろう?」という視点を持つようになったことです。表層的な経験やスキルよりも、その人が何にワクワクするのか、何に好奇心を持っているのかに着目するようになりました。
荻原:具体的に仕事でどのように活かされていますか?
松下:例えば、仕事でご一緒する社内外の方と対話する際に、その方の言葉の背景にある意図や動機を考えるようになりました。「こういう意図があって言っているのかな」と想像し、その仮説をぶつけることで、より深いコミュニケーションができるようになった気がします。
また、新たな求職者との面接の際にも、表層だけで捉えず、その方の原動力やポテンシャルに目を向けるようになりました。これによって、単に「人と付き合う」というよりも、人との関わりを楽しめるようになったと感じています。
荻原:相手の言動の背景にある原動力を考えることで、コミュニケーションが変わったのですね。
松下:その通りです。
4. 「人を選ぶ技術」はどんな人におすすめ?

荻原:この本はどのような方におすすめですか?
松下:ビジネスパーソン全般におすすめです。新入社員の方であれば、「どういう視点で会社が人材を見ているのか」を知る手がかりになりますし、誰かのメンターになった方、部下を持つ方には特に役立つと思います。
また、人と関わってうまくいかないと感じている方にも良いかもしれません。「こういう見方を見逃していたのか」という気づきがあるかもしれません。
荻原:最後に、この本から得られる一番のメリットは何だと思いますか?
松下:人の表層だけではなく、その源泉や本質を知ろうとする着眼点を得られることだと思います。
普段、何気なく人と接している中でも、一歩立ち止まって「この人の原動力はどこにあるのだろう?」と考えるようになりました。そういった視点があるだけで、人との関わり方やビジネスの質がぐっと深まる気がします。
人の「表層」ではなく「源泉」を見つめる視点。それこそが、これからの時代に求められる“選ぶ力”なのかもしれません。
荻原:ありがとうございました。人を見る目が養われる、とても示唆に富んだ本ですね。ぜひ読んでみたいと思います。
松下:こちらこそありがとうございました。ぜひ多くの方に手に取っていただきたい一冊です。
本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒経営×人材の超プロが教える 人を選ぶ技術
【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。
営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。
ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。
荻原エデル
社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。
趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。
keiko matsushita
株式会社アルヴァスデザイン・マーケティング担当。
大学卒業後、大手電機メーカーでシステム営業を経験。
2014年よりアルヴァスデザインへ参画。
旅と犬をこよなく愛する1児の母。