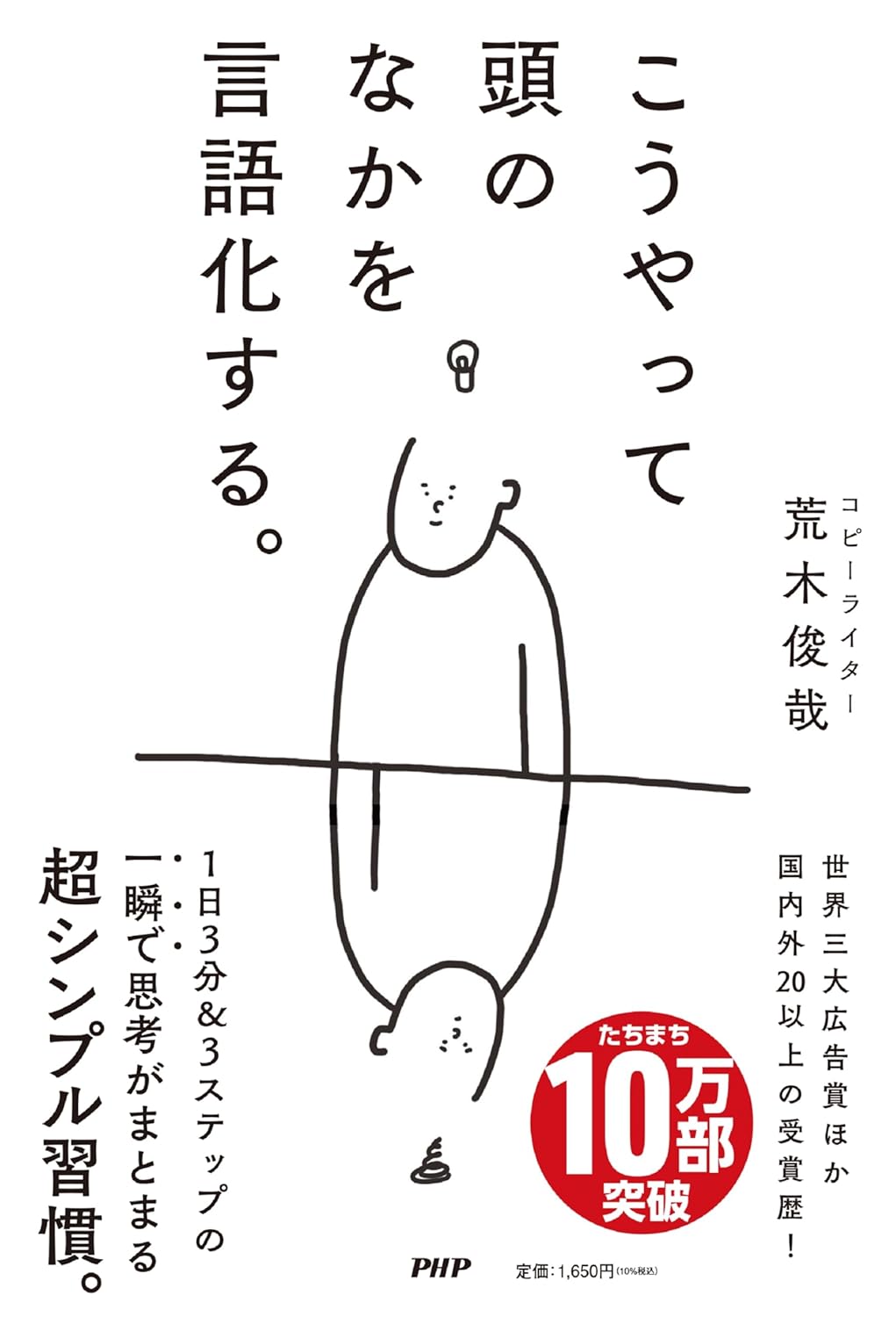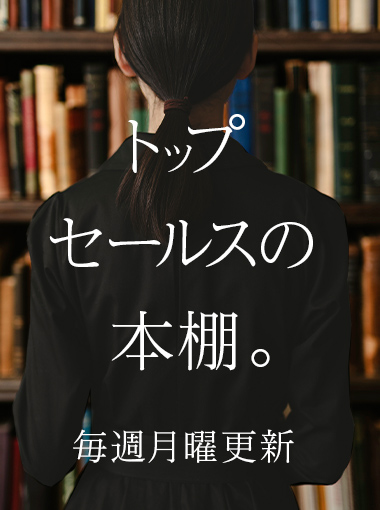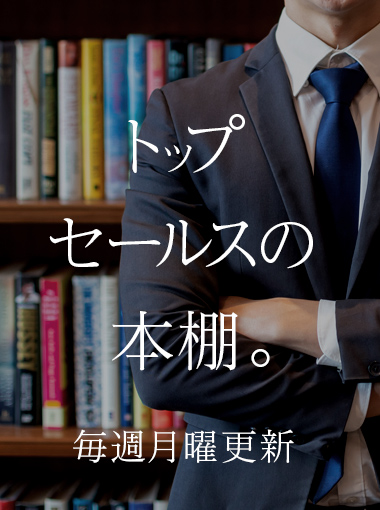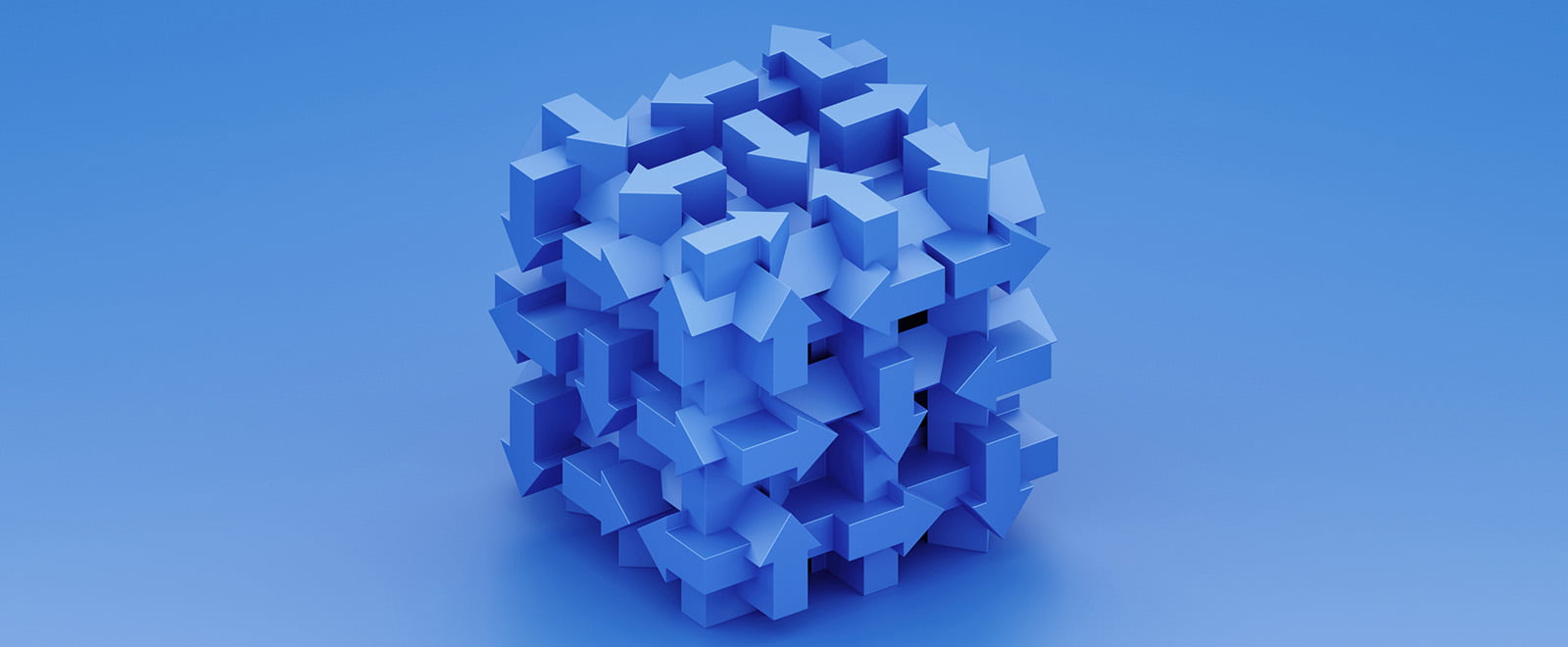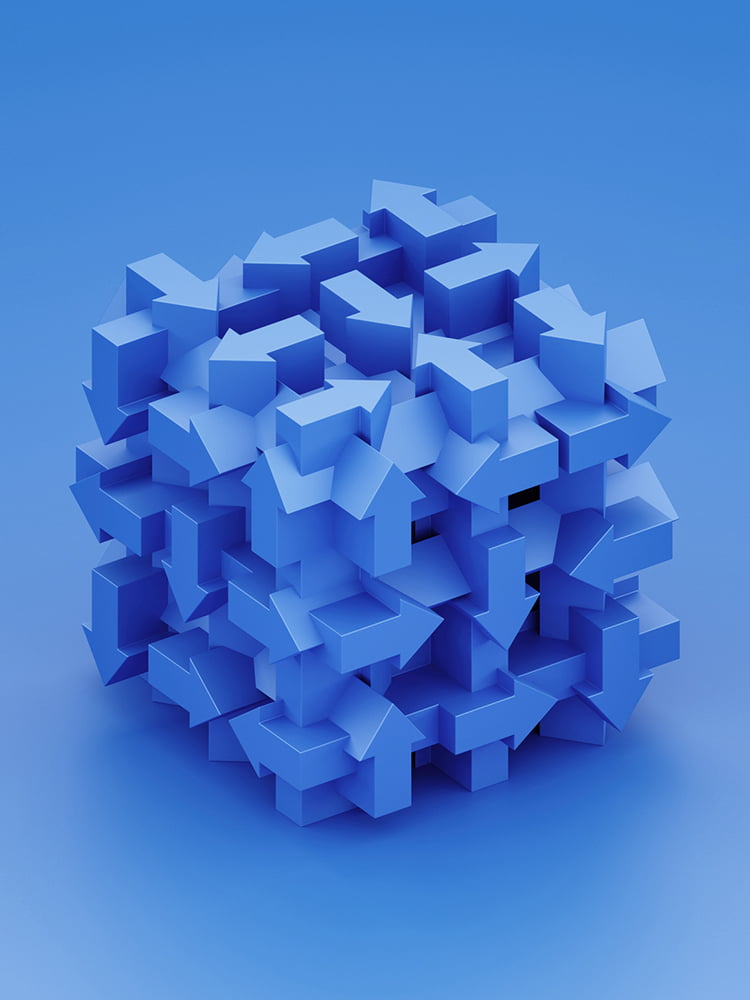こうやって頭のなかを言語化する。(荒木 俊哉著 2024年 PHP研究所)~言語化と伝え方の違いを理解して、真の表現力を身につける~
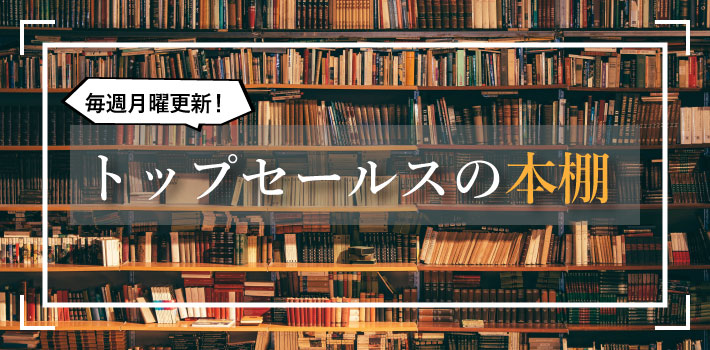
こんにちは。荻原です。
今回も引き続き、トップセールスの本棚をインタビュー形式でお届けしていきます。本日、インタビューに答えてくださったのは、アルヴァスデザインでプロデューサーとして活躍をしている松本さんです。
自身の言語化に課題感を持ち、解決の糸口を求めて手に取った一冊から得た気づきと実践について、詳しくお話を伺いました。是非、ご一読ください。
目次
1. 「こうやって頭の中を言語化する」はどんな書籍?

荻原:本日は、よろしくお願いします。まず、松本さんがご紹介する書籍について簡単に教えてください。
松本:はい、私が今日紹介するのは『こうやって頭の中を言語化する』という本です。コピーライターの方が執筆されているのですが、とても読みやすく、質感の良い本です。
私は普段から言語化ということを自分の中で課題に感じていて、どんなふうに取り組んでいけば上達するかを考えていた時に、本屋さんで気になって選んだ一冊です。
荻原:表紙もとても優しそうで、内容に入っていけそうな印象ですね。著者の方はどのような経歴をお持ちなのですか?
松本:世界の三大広告賞のうち、二つの賞をダブル受賞されている方です。一橋大学などの大学でも広告のゼミ講師をされていて、20年ぐらいずっと広告業界に携わっている、まさに広告のスペシャリストですね。
コピーライターの方って、一言で伝えたい事を100も200も、その一言に込めるような感覚をお持ちですよね。そのメソッドがとてもわかりやすく書かれています。
2. 言語化と伝え方は全く別物

荻原:本書を読んで、特に印象に残ったポイントはありますか?
松本:一番印象に残ったのは、「言語化と伝え方は全く別物である」という考え方です。多くの方が言語化と伝え方を同じものだと思っている中で、それらは全く別物だということが書かれていました。
伝え方は「どう言うか」で、言語化は「何を言うか」なんです。もっと簡単に言うと、伝え方は料理でいうレシピで、言語化は食材みたいなものです。
荻原:レシピと食材という例えは、とてもわかりやすいですね!
松本:そうなんです。言語化で頭の中を整理して食材を準備できているのだけれども、それをいざ伝える時にそのままストレートに言うと、冷たい印象であったり、人によっては攻められていたりするように感じることがある。だから、言語化で頭の中で考えたことを伝える方法は、やっぱり別物として考えるべきだということが書かれています。
そして、言語化能力を養っていくことで、その伝え方自体も上手くなっていくという内容でした。
3. 実践的なフレームワーク「聞く→書く→まとめる」

荻原:本書では具体的なテクニックも紹介されているのですか?
松本:はい。本書の中心となるのは「聞く→書く→まとめる」というフレームワークです。特に印象的だったのは、「出来事と感じたことをメモする」という方法でした。
例えば、誰かと会話する中で「それについてどう感じましたか?」と聞かれても、なかなか答えにくいものです。でも、その前にまず具体的な出来事を思い出させて、「こういうことがあって、その時あなたはどう感じましたか?」という聞き方をすると、相手の言語化を誘うことができるといったことです。
荻原:なるほど。「言語化を誘う」という表現が面白いですね。
松本:そうなんです。言語化が上手い人は、まず人の話の聞き方が違うということが書かれています。キャリアコンサルタントの方を例に、どのように人の話を聞いて、相手の言語化を誘っているのかが具体的に解説されています。
荻原:実際の仕事でも応用できそうですね。
松本:本書では、コピーライターの方なので、例えば会社名を考える時にどのように聞くのか、その会社の社長さんが何を思って会社名を変えようとしているのかを言語化してもらうための聞き方の具体例が載っています。それを持ち帰って自分の中で一回書いてまとめたものをクライアントに提案するという流れです。
4. 「インフルエンサーは答えを持っていない」という気づき

荻原:本書で特に刺さった表現はありましたか?
松本:「インフルエンサーは答えを持っていない」という部分ですね。最近SNSを見ていると、自分が検索したことや不安に思っていることに関する情報がすぐに出てきますよね。それぞれ言っていることは違うけれど似通っているところもあって、つい「この人が言っているからやってみよう」という気持ちになってしまいます。
でも、それが合っているかどうかは関係なく、結局どうすればいいのかわからなくなって、余計もやもやが広がっていくのです。
荻原:確かに情報過多の現代では、よくある現象ですね。
松本:本書では、そういう情報に惑わされずに、結局自分が一番良いと思ったやり方、正解がない中で自分に聞くのが一番効率的だと言っています。
そして、その自分の軸をしっかり言語化するために本書が役立つという訳です。
5. 「継続は言語化力なり」- 実践による変化

荻原:実際に本書を読んで、日常的に変わったことはありますか?
松本:実際に「聞く→書く→まとめる」を始めました。その日の一番のトピックを「なぜ自分はそう感じたのか?」という視点で振り返ります。
今まで漠然とその時感じた感情はその場で終わっていたものが、その日の夜に振り返って「私はなぜ、この時にこう感じたのだろう?」と考えることで、同じような状況になったらまた思い出せる感情として自分の中で見える化できるようになりました。
荻原:それは素晴らしい変化ですね。具体例はありますか?
松本:例えば、「クライアントに褒められて嬉しかった」という出来事があったとます。それを「なぜ嬉しかったのか?」と紐解いていくと、最終的に「仕事で嬉しい瞬間はこういう瞬間だ」という普遍的な形で自分の価値観が見えてきます。これは自分自身の整理にもとても役立ちます。
本書でも「継続は言語化力なり」と書かれているように、言語化は後天的に得られる能力なので、継続していけば必ず積み重なっていくと思います。
6. 「こうやって頭の中を言語化する」はどんな人におすすめ?

荻原:この本はどのような方におすすめですか?
松本:まず、自分の言いたいことをうまく伝えられていないという経験をしている方ですね。特に営業職の方には強くおすすめしたいです。
お客様との商談で「どう思われますか?」と質問された時に的確に答えられなかったり、提案内容をうまく言葉にできなかったりする経験は、営業の方なら誰でもあると思います。
本書の「聞く→書く→まとめる」フレームワークは、お客様のニーズを正確に聞き出したり、自分の提案を整理して伝えたりする場面で直接活用できると思います。
荻原:確かに営業の現場では言語化する力が重要ですね。
松本:そうなんです。でも、それだけでなく、人生に悩んでいる方にも役立つのではないかと思います。自分の理解を深めていくことで、人生に悩んだ時に自分がどうしたいのかが結果として見えてくると思います。
本書には人生の悩みへの直接的な回答が載っているわけではないですが、自分の理解を深めるためのやり方が載っているので、悩んでいるけれどどうすればいいのかわからないという人にもおすすめできます。
荻原:つまり、自分自身で解決策を切り開いていきたい方に特に響きそうですね。
松本:そうですね。営業職の方をはじめ、自分なりに課題感を持っている方や悩んでいる方におすすめです。誰かに解決してほしいという受け身の姿勢の方よりも、自分で向き合っていきたいという方により適していると思います。
荻原:本日は貴重なお話をありがとうございました。言語化の技術だけでなく、自分自身を理解するためのツールとしても活用できる、とても実践的な書籍だということがよくわかりました。
松本:こちらこそ、ありがとうございました。この本の魅力が少しでも伝われば嬉しいです。ぜひ多くの方に読んでいただきたい一冊です。
本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒こうやって頭のなかを言語化する。
【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。
営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。
ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。
荻原エデル
社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。
趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。
松本 有加里
群馬県出身。
大学卒業後、人材派遣会社で営業→事務と経験し2024年9月からアルヴァスデザインに入社。
趣味はアニメ・映画鑑賞。世界で一番嫌いなものは虫。