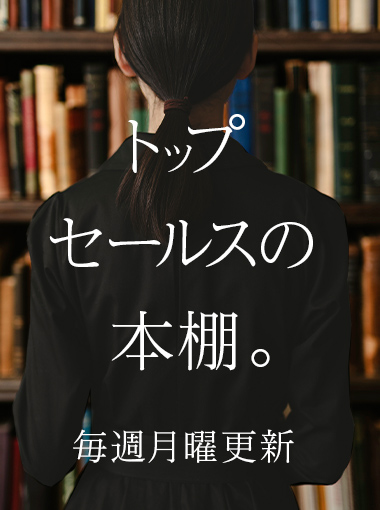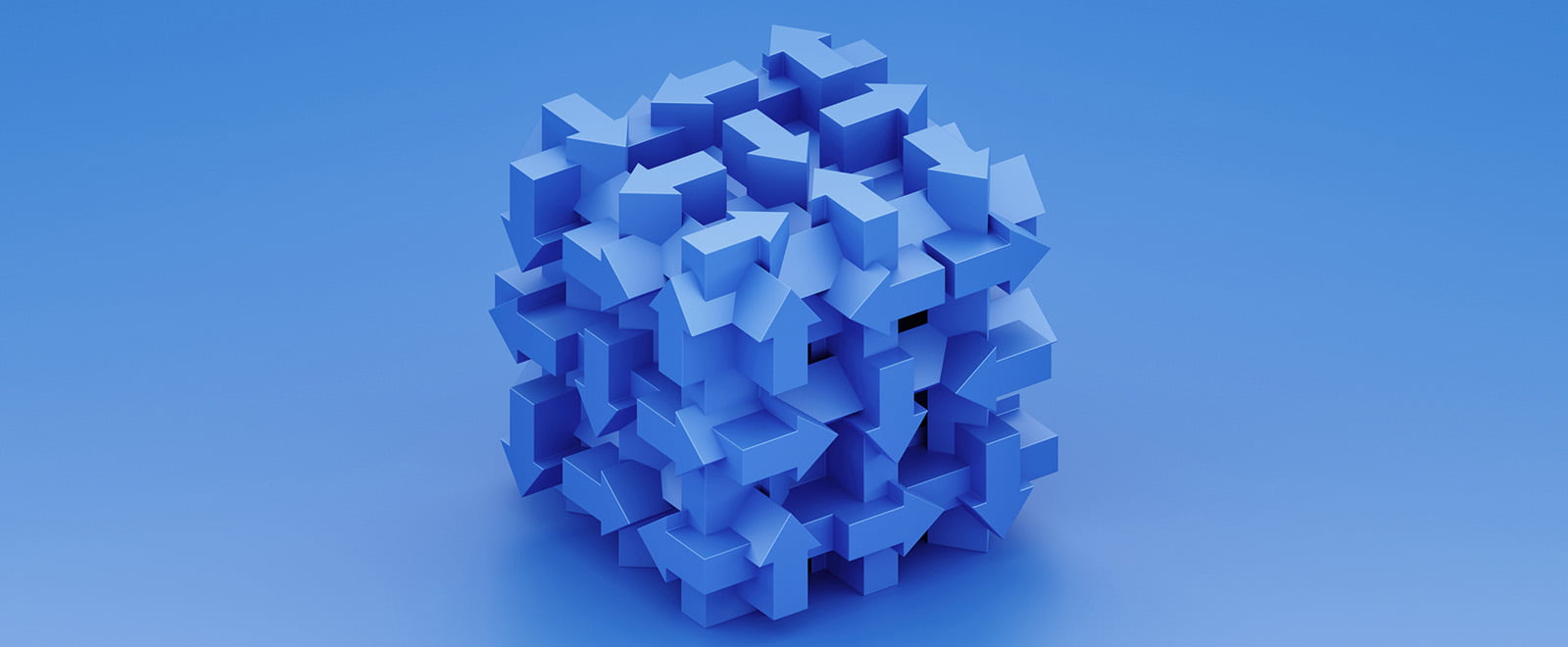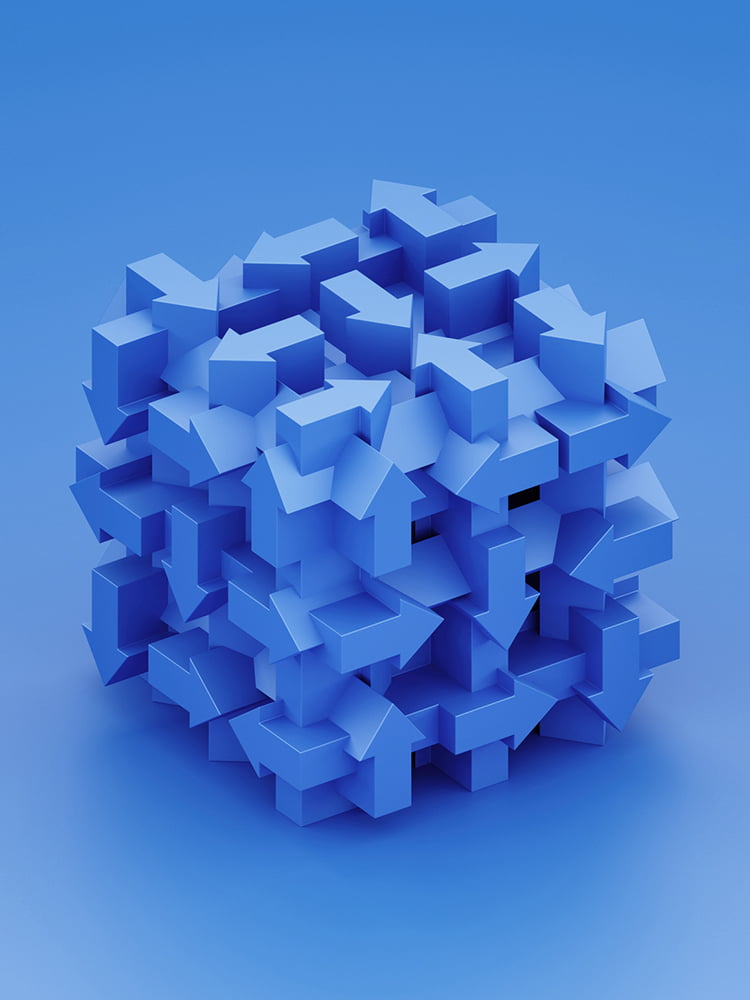<トップセールスの本棚>リーダーの言語化(木暮 太一著 2024年 ダイヤモンド社)〜明確化がチームを動かす力となる〜
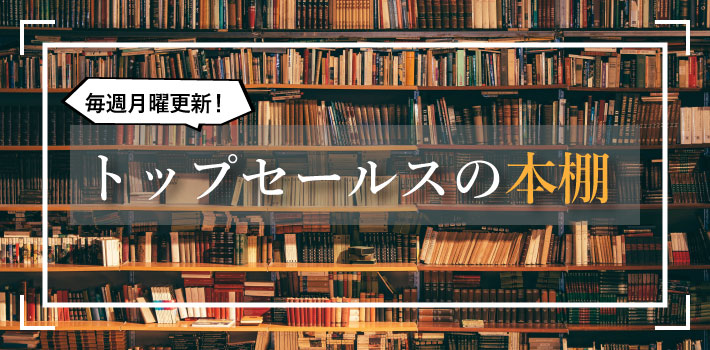
こんにちは。荻原です。
今回も引き続き、トップセールスの本棚をインタビュー形式でお届けしていきます。本日、インタビューに答えてくださったのは、アルヴァスデザインでマネージャーとして活躍中の松下さんです。
言語化コンサルタントとして注目を集める木暮太一氏の「リーダーの言語化」をピックアップ頂き、実体験を交えながら詳しくお話を伺いました。
是非、ご一読ください。
目次
1. 書籍「リーダーの言語化」の魅力とは?
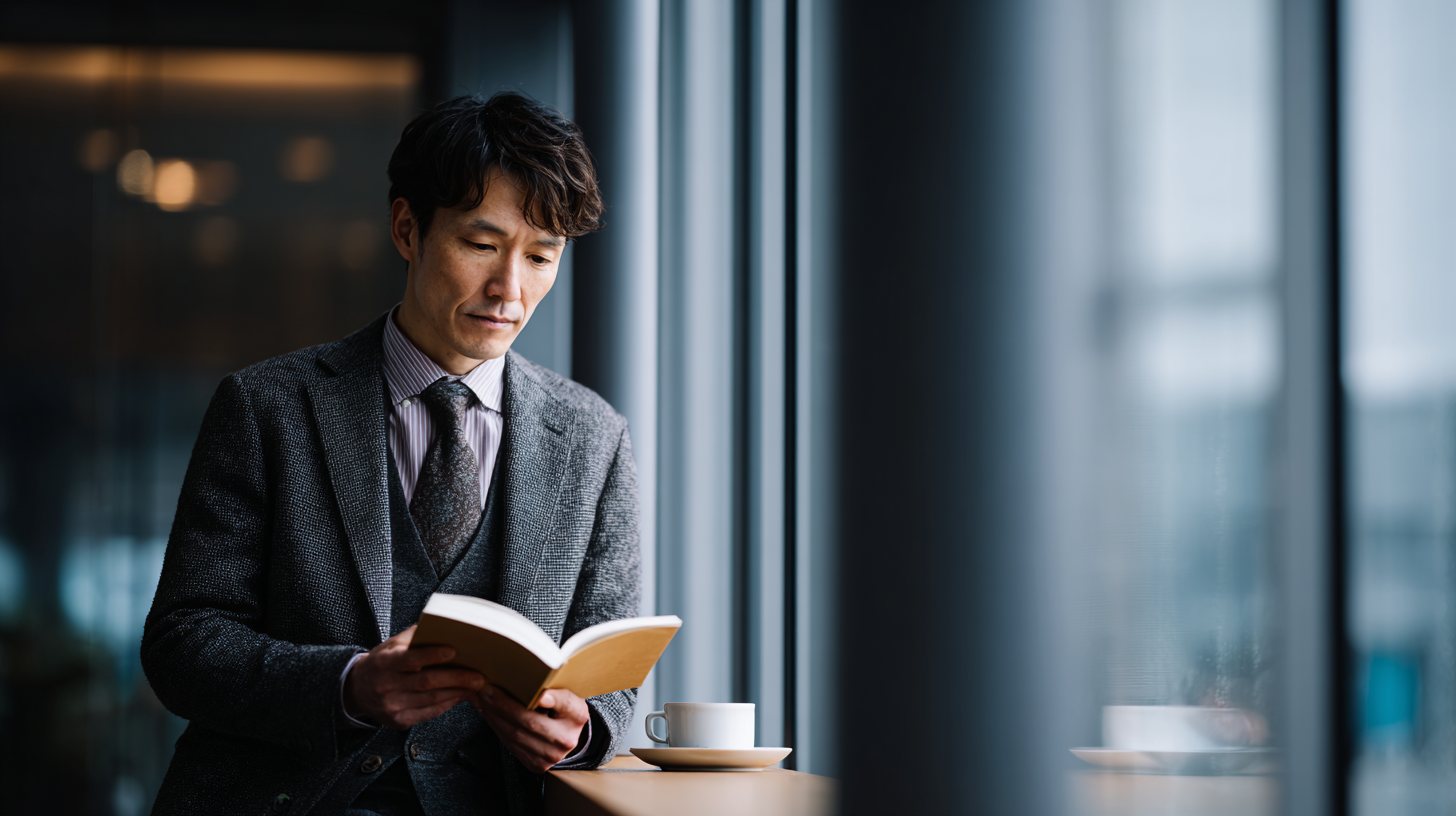
荻原:本日は、よろしくお願いします。はじめに、松下さんがおすすめする一冊について簡単にご紹介お願いします。
松下:今回私が紹介したいと思っている本は『リーダーの言語化』という書籍です。著者は木暮太一さんで、言語化コンサルタントとして活動されている方です。実は、木暮さんは以前『すごい言語化』という本も出されていて、こちらは2023年に出版されています。今回の『リーダーの言語化』は2024年10月に出版された、別の切り口での言語化の一冊になります。
荻原:なるほど。リーダーというところに焦点をあてた作品なのですね。
松下::はい。木暮さんの過去の書籍にも目を通していましたが、「言語化」というテーマを見て、今回もとても気になりました。
木暮さんご自身が非常に優秀な方で、子どもの頃からリーダーを任されることが多く、社会人になってからも飛び抜けたプレイヤーとして活躍されていたそうです。その結果、早くからリーダーの役割を担うことになり、そこで多くの苦労も経験されたと書かれていました。
そうした実体験から生まれた「言語化」だからこそ、内容に深みがあると感じました。
2. 時代背景から見る言語化の重要性

荻原:本書は具体的にどのような内容が書かれているのですか?
松下:本書の前段で、これまでの時代はリーダーがそこまで言葉で明確にしなくても「体で覚えろ」「見て学べ」といったことが通用してきたけれど、今はそうではないよね、ということが書かれています。
さらに現代は、「正解がない時代」というよりは、かつての正解も正解だし、若手のメンバーが新しく持ってきた正解も正解で、正解が増えているような状況です。正解が多すぎて、お互いの正解がぶつかり合っているのではないか、という問題提起をしています。
荻原:確かに、そういう場面に遭遇することもありますね。
松下:私もそう思いました。これまでの正解がすべてではなく、もしかしたら全く異なるところに正解がある時代だということを改めて自分の中で理解しました。
そんな時代においては、リーダーが自分の頭の中を明確に言語化し、伝えられるようになる必要があると思います。言語化によって、会社やプロジェクトの動き方も変わるし、チームもまとまるといった効果がありそうです。
3. 言語化の本質とは何か?

荻原:本書では、言語化についてどのように定義されているのでしょうか?
松下:本書では「言語化とは明確化である」ということを言っています。
言語化と聞くと、文字通り「言葉にすること」や「滑らかな言葉になっているか」とか「うまい表現をすること」と思われがちですが、そうではない。
「考えていることを明確にできているかどうか」が大事だと本書では語られています。
例え、言葉でなくて図形だったとしても、数字だったとしても、言語化できているということが書かれていて、なるほどと思いました。
言語にこだわる必要はないのだと。
荻原:確かに。今の時代は本当に頭の中に抱いていることをクリアにするのがすごく大事ですよね。
松下:その通りです。言語化という言葉を聞いた時に、一旦「明確化する」と置き換えて思考する癖をつけていきたいなと思いました。
実際に「言語化しよう」と考えた時と「明確化しよう」と思った時では、全然アプローチが違うと思います。そこを意識するだけでもアウトプットが変わりますよね。
4. 価値の明確化と実践方法

荻原:特に印象に残ったシーンはありましたか?
松下:はい。「価値を言語化する」という話はとても印象的でした。ビジネスシーンにおいて価値を言語化することは非常に重要ですが、本書では、価値を言語化するときの考え方として、三つのポイントが提示されています。
・一つ目が「価値は相手に変化を与えるものである」、
・二つ目が「価値は相手のテンションを上げるものである」、
・三つ目が「価値は相手に伝わらないほどの自分のこだわりである」
という三つです。
荻原:面白い観点ですね。
松下:はい。最終的にはこの三つに集約できるのではないかと書かれています。
例えば、この価値のポイントをメンバーとの共通の指針にして、「今回のこのプロジェクトのこのシーンでは、ここを大事にします。」みたいに会話をしていくと良いのではないかということですね。
異論がぶつかった時に、別にそっちが間違っているよという否定をしているわけではなく、「今回はこちらを大事にして決めましょう」といったコミュニケーションが取れてくると良いだろうなと思いました。
5. 実務での活用シーン

荻原:松下さんが今後、実際の業務の中に取り入れてみたいと思った部分はどこでしょうか?
松下:まず取り入れてみたいのが「価値の明確化」です。
たとえば新規プロジェクトの企画会議では、複数案のどれも良くて決めきれないことがあります。
そんな時に、「この案の一番の価値は何か?」とメンバーに問いかけることで、議論が噛み合いやすくなると感じました。
今後の会議では、まず“価値の明確化”から始めてみたいです。
荻原:なるほど。相手の目的を捉えようとするということですね。
6. 「リーダーの言語化」はどんな人におすすめ?

荻原:この本は、どのような方におすすめできますか?
松下:基本的には、全てのビジネスパーソンにぜひ一度読んでほしいです。
役職問わず、どの役職でも言語化は必要だからです。どなたが読んでも「なるほど」と思える内容だと思います。
既に分かっている人にとっても、思考が整理されますし、逆にビジネスパーソンなりたての若手の方たちは、最初にこれを読んでおくと、お仕事がスムーズになるのではないかと感じています。
荻原:確かに、若手の方には特に良さそうですね。
松下:そうですね。上司とのやり取りにも役立ちますし、営業パーソンの場合であればお客様とのやり取りのヒントになると思います。
また、セルフマネジメントの観点でも非常に役立つと感じました。
自分の思考を整理する際に、本書で紹介されている視点を使って問いかけるだけでも、頭の中がクリアになります。
たとえば営業であれば、商談準備の段階、
「今回、お客様にどんな価値を提供できるか?」
「その価値は、相手にどんな変化をもたらすのか?」
と自問するだけでも、提案の軸が明確になります。
荻原:「言語化=明確化」という本書の核心的な考え方は、確かに多くのビジネスシーンで活用できそうですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。
松下:こちらこそ、ありがとうございました。言語化と聞いたときに、明確化に置き換えて思考するだけでも、きっと結果が変わるのではないかと思います。ぜひ皆さんにも手に取っていただきたい一冊です。
本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒リーダーの言語化
【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。
営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。
ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。
荻原エデル
社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。
趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。
keiko matsushita
株式会社アルヴァスデザイン・マーケティング担当。
大学卒業後、大手電機メーカーでシステム営業を経験。
2014年よりアルヴァスデザインへ参画。
旅と犬をこよなく愛する1児の母。