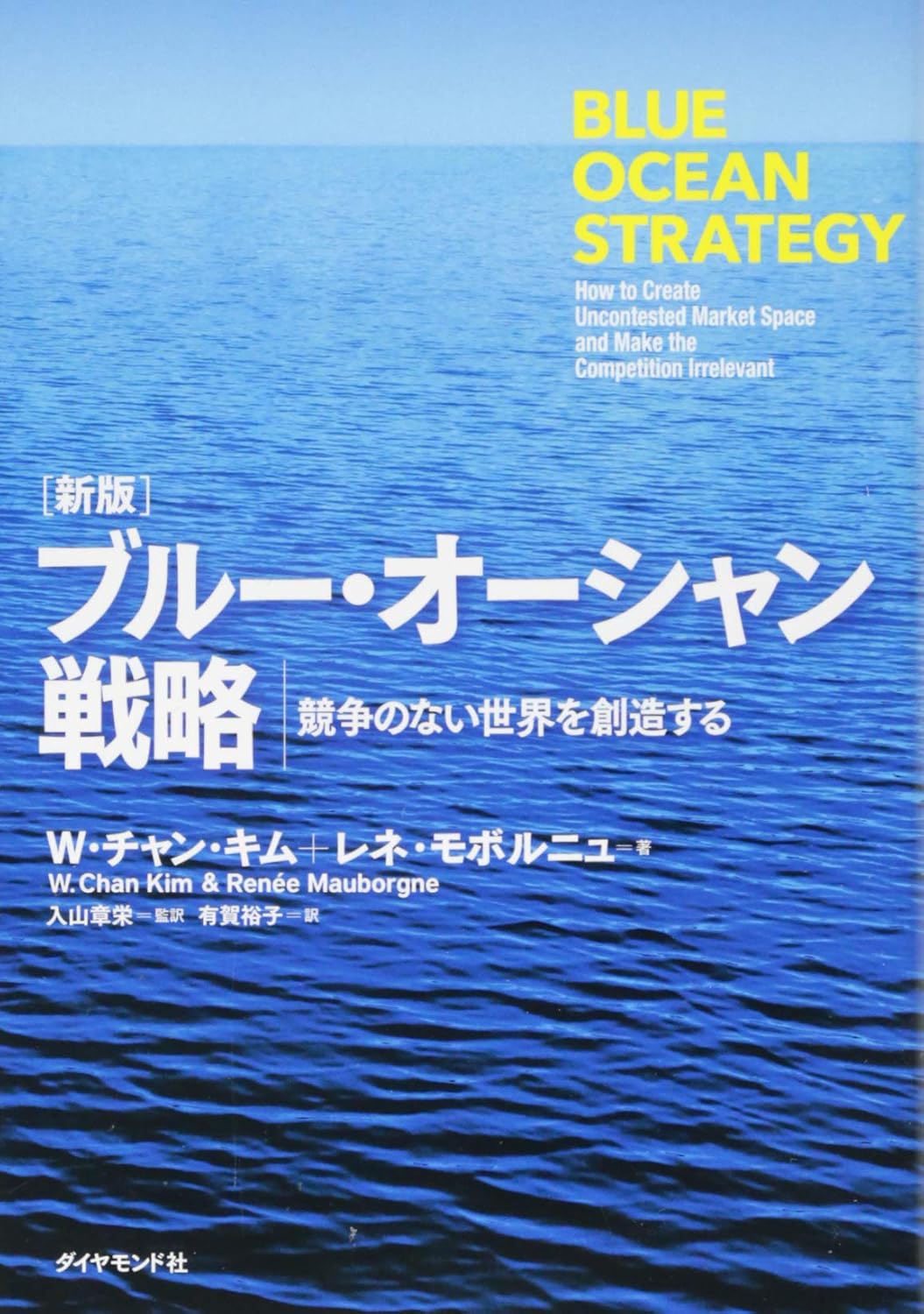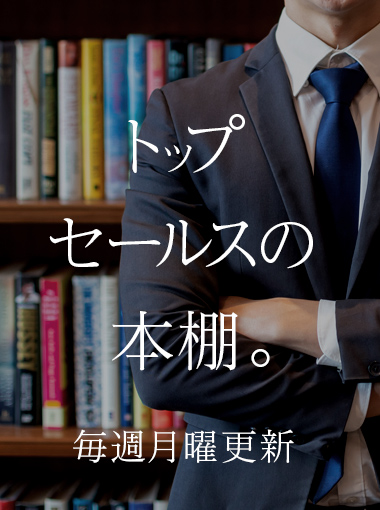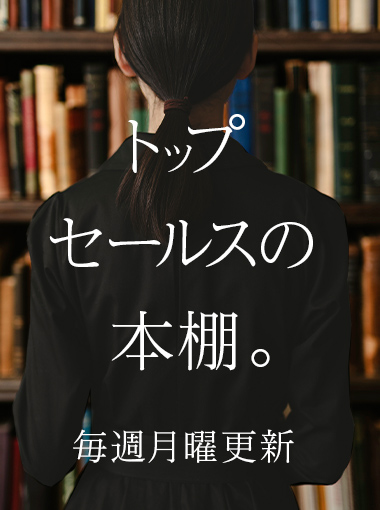「ブルー・オーシャン戦略 競争のない世界を創造する」(W・チャン・キム、レネ・モボルニュ著 2005年 ランダムハウス講談社)〜ブルー・オーシャンで切り開く新たな市場〜
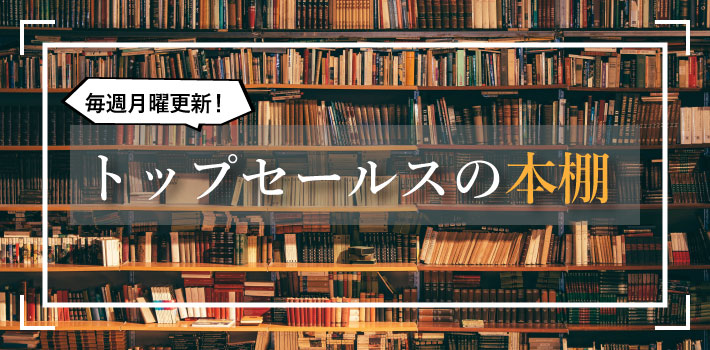
こんにちは。荻原です。
本日は、競争から脱却し新たな市場を切り開く戦略として世界中で注目される「ブルー・オーシャン戦略」をご紹介したいと思います。
本書は、INSEAD(欧州経営大学院)のW・チャン・キム教授とレネ・モボルニュ教授によって著され、2005年の発刊以来、ビジネスパーソンのバイブルとして読み継がれています。
競争が激化する現代において、「いかに競争を避けるか」という問いは、起業家だけでなく、日々の営業活動に取り組むすべてのビジネスパーソンにとって大きなヒントとなるはずです。それでは早速見ていきましょう。
目次
1. レッド・オーシャンとブルー・オーシャン

本書では、市場を二つの「海」に分類して説明しています。
一つは「レッド・オーシャン」。これは既存の産業を表す言葉です。
「レッド・オーシャンでは各産業の境界はすでに引かれていて、誰もがそれを受け入れている。競争のルールも広く知られており、各社ともライバルをしのいで、限られたパイのうちでできるだけ多くを奪い取ろうとする。競争相手が増えるにつれて、利益や成長の見通しは厳しくなっていく。製品のコモディティ化が進み、競争が激しさを極めるため、レッド・オーシャンは赤い血潮に染まっていく。」
キム・W・チャン、レネ・モボルニュ.ブルー・オーシャン戦略.11版.ランダムハウス講談社.2006.294p.P20
一方の「ブルー・オーシャン」とは、競争のない未開拓の市場空間を指します。
「対照的に、ブルー・オーシャンは市場として未開拓であるため、企業は新たに需要を掘り起こそうとする。利益の伸びにもおおいに期待が持てる。ブルー・オーシャンの中には、これまでの産業の枠組みを超えて、その外に新しく創造されるものもあるが、大多数はレッド・オーシャンの延長として、つまり既存の産業を拡張することによって生み出される。」
キム・W・チャン、レネ・モボルニュ.ブルー・オーシャン戦略.11版.ランダムハウス講談社.2006.294p.P20
ここで重要なのは、ブルー・オーシャンは全く別の世界から生まれるのではなく、既存の産業の延長線上に創造されるということです。
つまり、私たちが今いる業界の常識を疑い、前提条件をずらしていくことで、ブルー・オーシャンが見えてくるのです。
本書では、斜陽産業だったサーカス業界で成功を収めた「シルク・ドゥ・ソレイユ」の事例が紹介されています。
従来のサーカスは子どもをメインターゲットとしていました。
しかし、シルク・ドゥ・ソレイユは「大人が楽しめるエンターテインメント」という新たな価値を提供しました。高額な出演料を払うスターや動物を使わないことでコストを抑えながら、テーマ性の高い洗練された演出で高付加価値を実現したのです。
このように、誰もが“当たり前”と思っていた前提を問い直すことで、既存市場の中にも新たな可能性が眠っているのかもしれません。
営業の現場に置き換えるなら──
「自社の業界ではこうするのが常識」
「このサービスはこのターゲットに売るもの」
そんな思い込みに、あえて違和感を持ってみることが、競争から一歩抜け出すヒントになるのではないでしょうか。
2. 4つのアクション:新たな価値曲線を描く

それでは「競争を無意味にするほどの新たな市場」をどうやって生み出すのか。
本書が提唱するブルー・オーシャン戦略の中核にあるのが、「差別化された価値」と「低コスト」を同時に実現する考え方です。
この考え方を実践するために、本書で紹介されているフレームワークが「4つのアクション」です。
4つのアクションとは、業界の常識に対して次の問いを投げかけることです。
- 取り除く:業界常識として備わっている要素のうち、取り除くべきものは何か?
- 減らす:業界標準と比べて思いきり減らすべき要素は何か?
- 増やす:業界標準と比べて大胆に増やすべき要素は何か?
- 付け加える:業界でこれまで提供されていない、今後付け加えるべき要素は何か?
シルク・ドゥ・ソレイユの事例では、花形パフォーマーや動物によるショーを「取り除き」、笑いやスリルを「減らし」、テーマ性や芸術性の高い演出を「付け加え」ました。
私も、日々、資料を制作したり、営業担当者と会話をしたりする中で、
「これって本当に必要だろうか?」
「お客様にとって過剰になっていないだろうか?」
と感じる場面があります。
そんな違和感をもとに、少し視点をずらしてみることで、
これまでとは違った提案のヒントが見えてきたこともありました。
4つのアクションを取り入れることで、ブルー・オーシャン的な考え方ができる余地はまだある、そんな気づきが、この章を通じて得られたように思います。
3. 市場の境界を引き直す:6つのパス

次に、ブルー・オーシャンを創造するための具体的な方法として、本書では「市場の境界を引き直す6つのパス」が提示されています。
- 代替産業に学ぶ:同じ目的を果たす異なる形態の製品やサービスから学ぶ
- 業界内の他の戦略グループから学ぶ:高級路線と低価格路線など、異なる戦略グループの良いところを組み合わせる
- 別の買い手グループに目を向ける:購買者、利用者、影響者など、異なる買い手グループに焦点を当てる
- 補完財や補完サービスを見渡す:製品・サービスと併用されるものに着目する
- 機能志向と感性志向を切り替える:機能性重視の業界に感性を、感性重視の業界に機能性を持ち込む
- 将来を見通す:トレンドが顧客価値にどう影響するかを考える
これらのパスは、業界の常識や前提を疑い、新たな視点で市場を見直すことを促します。
例えば、任天堂のWiiは、画質などの性能競争から離れ、「誰でも直感的に操作できる」という新しい価値を提供しました。Wiiリモコンという革新的なコントローラーにより、子どもだけでなく、幅広い世代に受け入れられたのです。
これは、ゲーム機の性能を「減らし」、直感的な操作性を「増やした」事例と言えます。
私自身も模索中ではありますが、業務の中でこういった視点を持つことで、
「意外と見落としていたお客様のニーズ」や「競合が注目していない切り口」に気づける場面がありました。
完璧な答えはなくても、「ちょっと別の見方をしてみようかな」と思えることが、次の一手を見つけるきっかけになる気がしています。
この視点は、営業現場で提案やターゲット選定に悩んでいる方にとっても、新しい打ち手を考えるきっかけになるのではないかと思います。
4. おわりに

いかがでしたでしょうか。
ブルー・オーシャン戦略は、「競争を避ける」という単純な話ではありません。コストを下げながら価値を高めるという、一見矛盾する課題に真正面から取り組む戦略なのです。
もちろん、ブルー・オーシャンを見つけたからといって、それで安泰というわけではありません。本書でも指摘されているように、ブルー・オーシャンが成功すれば、模倣者が現れるのは時間の問題です。
したがって、ブルー・オーシャンを開拓し続けると同時に、既存市場での競争力も維持する必要があります。つまり、ブルー・オーシャンとレッド・オーシャンの両方で繁栄する能力が求められるのです。
営業担当者として、日々の競争に追われる中で、「そもそも競争しなくてもいい市場はないか?」「業界の常識を疑ってみたらどうなるか?」という視点を持つことは、非常に重要です。
本書が提示する戦略キャンバスや4つのアクション、6つのパスといったフレームワークは、そうした視点を持つための有効なツールになるはずです。
皆さんも、自分の営業活動において、小さなブルー・オーシャンを見つけてみてはいかがでしょうか。
自分なりのブルー・オーシャンを探すことは、決して特別なことではありません。
日々の業務の中でふとした視点のズレに気づけたとき、そこに次のチャンスが潜んでいるかもしれません。
本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒ブルーオーシャン戦略
【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。