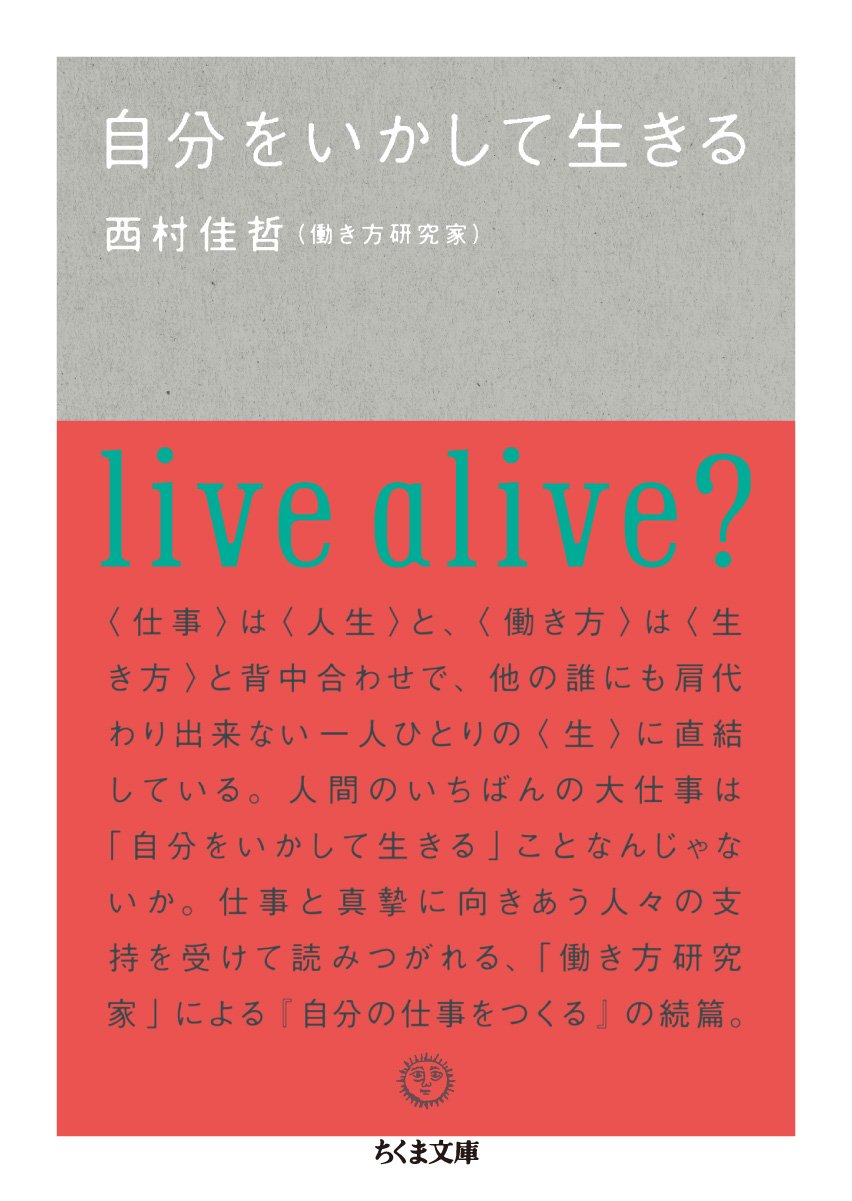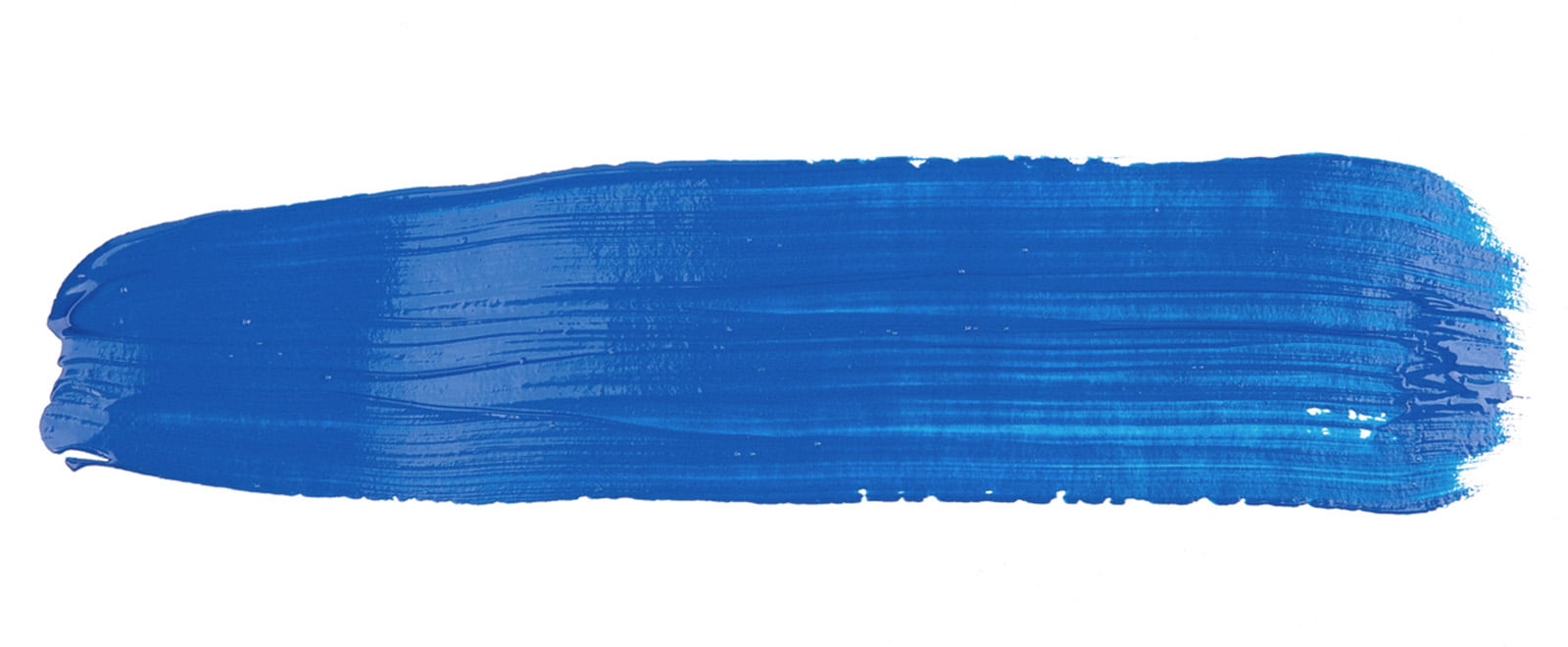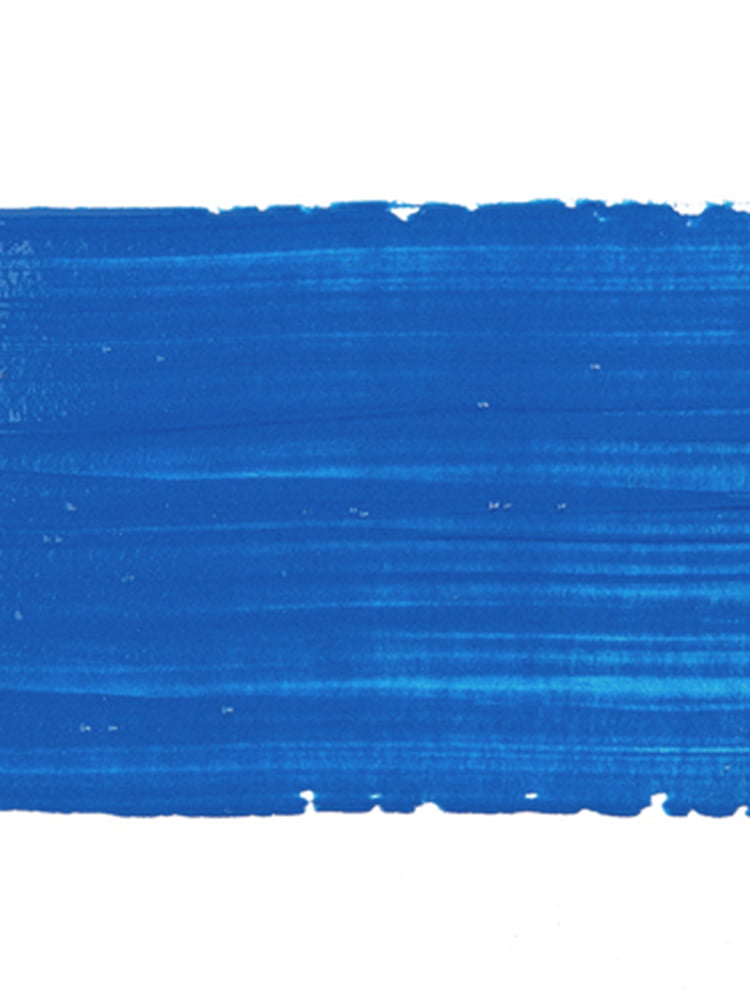<トップセールスの本棚>自分をいかして生きる(西村佳哲著 2009年 バジリコ社)~「心の羅針盤」が指し示す本当の仕事~

こんにちは。荻原です。
今回も引き続き、トップセールスの本棚をインタビュー形式でお届けしていきます。本日、インタビューに答えてくださったのは、仕事の本質について日々向き合っている土岐さんです。
働くことの意味、自分らしい仕事とは何かを深く問いかける一冊「自分をいかして生きる」をご紹介いただきました。効率や成果が重視される現代だからこそ、立ち止まって考えたい「仕事」の本質について語っていただきました。
是非、ご一読ください。
目次
1. 「自分をいかして生きる」はどんな書籍?

荻原:本日は、よろしくお願いします。はじめに、土岐さんがおすすめする一冊について簡単にご紹介お願いします。
土岐:今回ご紹介したいのは、西村佳哲さんの『自分をいかして生きる』という本です。西村さんは「働き方研究家」という肩書きで活動されている方で、もともと武蔵野美術大学でインテリアデザインを学び、設計事務所や大手ゼネコンでお仕事をされていました。
荻原:建築関係のお仕事をされていたのですね。
土岐:はい。でも、30歳の時に「自分に合っていない」と感じて会社を辞められたそうです。そこから「働き方研究家」として、ものづくりに携わる人たちを取材し、これからの生き方について記事を執筆するようになられました。今ではデザイナーや物書き、大学講師など、多様な活動をされている方です。
荻原:なるほど。その西村さんが書かれた本ということですね。どんな内容なのでしょうか?
土岐:この本は、まるで長い手紙のような書き方になっています。働くことの意味や、自分の仕事とは何かについて、様々な問いかけをしてくる一冊です。非常に売れている本で、産休・育休で立ち止まる時期や、退職のタイミングで読まれている方が多いようですね。
2. 現代の働き方への鋭い問題提起

荻原:本書の中で、特に印象に残ったポイントはどんなところでしょうか?
土岐:まず、冒頭から強烈な問題提起があります。
「物が溢れている時代に、みんな一生懸命働いているのに、なぜか世界は空虚になっている感じがする」と。
その理由として、本書では「こんなもんでいいでしょう」という妥協が、成果物に表れてしまうと指摘しています。
荻原:確かに、そういう感覚わかります。
土岐:本書にはこう書かれています。「こんなもんでいいでしょう、という感覚の中で行われた仕事は、同じ感覚を人に移す」と。その妥協や諦めが、どうしてもものづくりの中で見えてしまうのですね。
荻原:深いですね。成果物にその人の姿勢が表れるということですね。
土岐:はい。本書では「氷山の一角」という比喩が使われています。
最終的な成果として見えているのは氷山の一角で、その下には技術や知識があり、さらにその下には考え方があり、一番深いところには、その人の「あり方」や「存在」がある。
空虚な成果物が生まれる原因は、その土台に「こんなもんでいいでしょう」という考え方があり、さらにその奥には「従業員モード」として指示を受け取って出すだけの姿勢があるからだ、と説明されています。
荻原:なるほど。非常に鋭い切り込みですね。
3. 「働くことは本当に喜びなのか」という根本的な問い

荻原:他に印象に残っている内容はありますか?
土岐:「働くことは本当に喜びなのだろうか」という章があって、そこがとても考えさせられました。西村さんはデザイン教育にも携わっているのですが、その経験から感じた違和感が、本書の中で丁寧に語られています。
荻原:どんな違和感でしょうか?
土岐:デザイン教育が「作り方の伝授」に偏りすぎているという点です。これだけ物が溢れている世界で、なぜ「作る」ことが当然の前提になっているのか、と。学生たちは作ることを教わるけれど、そもそも「作るべきか、作らざるべきか」を考える機会がない。
荻原:確かに、「作ること」自体を疑う視点は新鮮ですね。
土岐:私もそう思いました。そして、これは私たちの「働き方」にも同じことが言えます。社会では「働くことは人間の本質だから良いことだ」というのが受け入れられやすい考え方ですよね。でも、本書ではこの考え方自体が、実は人類史の途中から現れたものだと指摘しています。
荻原:それは初めて聞きました。
土岐:産業革命の時代に、権力者が市民に働いてもらうために作られた価値観だ、と。つまり、デザイン教育で「作ること」が無条件の前提になっているのと同じように、私たちの社会でも「働くこと」が無条件の前提になっている。その前提自体を一度疑ってみることが大事だというメッセージです。
荻原:なるほど。デザインの話は、働くことの比喩だったのですね。
土岐:まさにその通りです。ただ、西村さんは「作るのをやめよう」「働くのをやめよう」と言っているわけではありません。作る・作らないを含めて、できるだけニュートラルな状態で、自分とデザインの関係性を感じて考える時間を過ごしても良いのではないか、と提案されています。
荻原:つまり、働くことについても同じように考えろということですね。
土岐:そうです。働くのが当たり前、と思考停止するのではなく、「なぜ働くのだろう」「なぜ働くなかで苦しみや喜びを感じるんだろう」と考え続けていくことが大事だと思います。もちろん、働いているという実感が「生きている」という感覚につながるのは事実です。でも本書では、仕事は生きている実感を覚えやすい媒体の一つではあるけれど、それだけが自分たちの「生きる」を充足させるものではない、という視点を提示しています。無条件に「働くべき」と思い込むのではなく、自分にとって働くとは何なのかを問い直すことが大切だと。
荻原:前提を疑うことの重要性を、デザイン教育の例を通して説明しているということですね。とても腑に落ちました。
4. 「思わず手が伸びる」仕事との出会い

荻原:本書では、どのような仕事が理想的だと語られているのでしょうか?
土岐:ここが本書の核心部分なのですが、営業マネージャーのエピソードが出てきます。そのマネージャーは、営業目標を数字で共有する、獲得件数のグラフで競争を煽るといったことをするのではなく、本人の意識をちゃんとお客さんの方に向けることが大事だと考えていました。
荻原:お客様志向ということですね。
土岐:そうです。スタッフの話を聞きながら、お客さんの話が出てきた時に強く共感したり反応したりすることで、「お客さんの方向に向かうのが良いのだな」ということが自然と了解されていく。本人の喜びにもなり、そのサイクルを回していくことで、チームの成績を底辺ラインから引き上げたそうです。
荻原:素晴らしい事例ですね。
土岐:ただ、本書の真髄はここからです。「売り上げを伸ばしたい会社があって、成績を上げたい部門のマネージャーがいて、成果を出したい営業スタッフがいて、より意識の高い営業活動を受けるお客さんがいる。この話はどこを切っても申し分ないけれど、僕には微妙な後味が残る」と書かれています。
荻原:もう少し詳しく教えて頂けますか?
土岐:「ここで発揮されたのって、本当に本人の力なのだろうか?」という問いかけです。その力は、教育の影響、親の期待、会社の理念や意図など、外部からの影響で動かされているだけではないか、と。
荻原:なるほど。確かに深い問いですね。
土岐:ここで、舞踏家の方の言葉が引用されています。「咲いている花を見て、あぁ綺麗だなぁ。いつの間にかそばに近寄って、花に向けて手が伸びる。この手は一体何なのだろう」と。
荻原:めちゃくちゃ深いですね。
土岐:花を摘むという行為ではなく、その直前の「思わず生まれてくる動き」に注目しています。その伸びていく手は、行動しようと思って行動しているわけではない。肉体を超えた魂の動きのようなもので、美しいものに触れようと近づいていく衝動という訳です。
荻原:それが本当の仕事につながるということですか?
土岐:そうです。自分を生かす仕事とは、「お客さまではいられないこと」「他の人には任せたくない」「思わず手が伸びてしまう」ような、自分の内側から湧き起こってくることによる動きで成り立つもの。それがかけがえのない自分の仕事になるのではないか、と本書は語っています。
5. 「心の羅針盤」を持つことの重要性

荻原:具体的な事例なども紹介されているのでしょうか?
土岐:はい、印象的な事例がいくつか紹介されています。その中でも特に印象深かったのが杉並区にある「黒森庵」という蕎麦屋さんの加藤さんの事例です。この方は元ソニーのデザイナーで、蕎麦屋さんになられた方です。
荻原:デザイナーから蕎麦屋さんへ、大きな転身ですね。
土岐:この方が言っているのが「心は人生の羅針盤だ」ということです。いつでも自分の胸を覗き込んで、今何を考えているか確認する。もっと話したいとか、ちょっと飽きてきたとか、本心って結構はっきりしているものだから、食べたくないものが出てきたら、ちゃんと「食べたくないです」と言えばいい、と。
荻原:シンプルだけど、なかなかできないことですよね。
土岐:はい。社会に適応していく上で、遠慮したり体裁を気にしたりするようになりますが、この方は我慢することで何かを見つけるのではなくて、本当にやりたいことをやる、という姿勢を貫いていらっしゃいます。実際、お子さんが五人いらっしゃって、三人の娘さんは高校に行かないと自分で決めて、一緒にお店をやっているそうです。
荻原:それはすごい決断ですね。
土岐:自分自身が決めた枠組みを忠実に守り切るというよりも、どっちの方向に心が向いているのだろう、と内側と対話しながら進んでいく。それが今の仕事をより楽しくする上でも大事だし、自分自身の転機が来た時に動くための気づき方や感じ方を磨くことにもつながるのだと思います。
6. 本書が与えてくれた変化

荻原:この本を読んで、土岐さんご自身の仕事の仕方で何か変化はありましたか?
土岐:自分自身が中身の詰まった成果物を出せているかどうか、ということを常に問いとして持ちたいと思うようになりました。本書に「人が一番傷つく時って、自分自身で自分自身を裏切った時なのではないか」という言葉があります。
荻原:確かに、それは一番辛いかもしれません。
土岐:自分が「いいな」って思える仕事ができたかどうか、そこに真摯に向き合っていきたいと思うようになりました。まだまだ未熟者なので、実際にそれだけのことをやれているかはわかりません。ですが、これからも働き続けるときの志として、この問いを持ち続けたいとです。
7. 「自分をいかして生きる」はどんな人におすすめ?

荻原:最後に、この本はどんな方におすすめですか?
土岐:自分の仕事を改めて見つめ直してみたい、立ち止まりたいと思っている方におすすめです。本書を読んでいると、ところどころで、自分が思っていた世界とは違う世界が見えてきます。「えっ、なんでそうなるの?」とか「あ、この人はそう思うのか。私はどう思うかな?」と、一緒に問いかけ合う感覚で読むことができます。
荻原:迷った時の原点、問いの原点になりそうですね。
土岐:そうですね。現代の「主体性がない」という問題の根源も、この本を読むと見えてきます。「個(=自分自身)として働く」のか、それとも「従業員モード」でやれと言われたことをただやるのか。そのあり方の違いで、プロセスも考え方も全然違ってきます。
荻原:主体性の根源には、覚悟を持って生きているかどうかがあるということですね。
土岐:まさにその通りです。最後に、本書の締めくくりの言葉をご紹介したいのですが、
「やらされてやるような労働はしたくないし、してほしくもない。どんな難しさがあろうと、一人一人が自分を突き動かしている力、この世界に埋もれてきた力を働きに変えて、つまり、自分の仕事をすることで社会が豊かさを得る。そんな風景を本当に見たいし、自分もその一端で働き生きていきたい」
と書かれています。
荻原:素晴らしいメッセージですね。
土岐:私自身も、自分の仕事をその一端で担えるように、常に自分の「心の羅針盤」を確認しながら進んでいきたいと思います。
荻原:心の羅針盤、大事にしたいですね。本日は非常に深いお話をありがとうございました。仕事の本質について考えさせられる、素晴らしい一冊のご紹介でした。
本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒自分をいかして生きる
【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。
営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。
ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。
荻原エデル
社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。
趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。
土岐優
石川県金沢市出身。音楽大学(ハープ科)卒業後、ファンマーケティングのリーディングカンパニーに勤めたのち、プロデューサーとしてアルヴァスデザインに参画。2024年10月よりナレッジ・マネジメント部を立ち上げ、ナレッジコーディネーター兼ラーニングデザイナーとして奔走中。趣味は内面探求、読書、マインドフルネス瞑想。好きな言葉は「強がらなくても大丈夫。どんなあなたも大好きだから。」