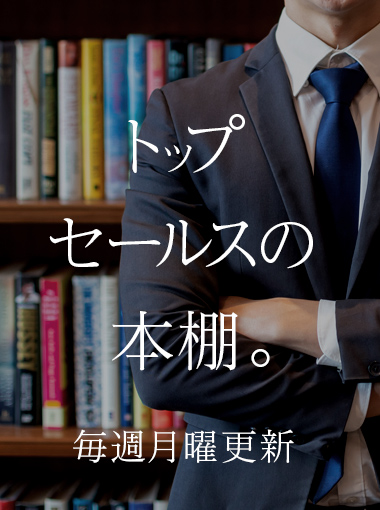なぜ働いていると本が読めなくなるのか(三宅 香帆著 2024年 集英社)~読書文化の変遷から考える「半身半分」の働き方~
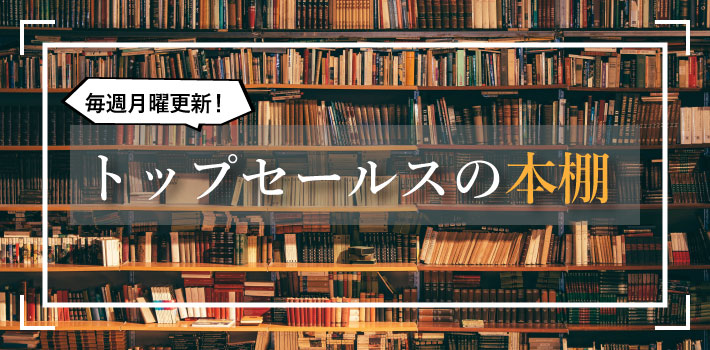
こんにちは。荻原です。
今回も引き続き、トップセールスの本棚をインタビュー形式でお届けしていきます。本日、インタビューに答えてくださったのは、アルヴァスデザインでプロデューサーとして活躍されている松本さんです。
若い世代の視点から「読書文化」と「働き方」の関係性を考察した一冊として「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」をご紹介いただきました。明治時代から現代に至るまでの日本人の読書習慣の変遷を辿りながら、現代社会における読書と仕事の両立について深く掘り下げた内容となっています。
是非、ご一読ください。
目次
1. 「読書と仕事の両立」を考える一冊

荻原:本日は、よろしくお願いします。早速ですが、松本さんのおすすめの一冊について簡単にご紹介お願いします。
松本:はい、今回ご紹介するのは『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という本です。本のタイトル通り、働いている現代人がなぜ読書をする時間を持てなくなっているのかについて、時代の変遷とともに解き明かしていく内容になっています。
荻原:なるほど。具体的にはどのような内容なのでしょうか?
松本:この本は、まず「仕事と読書はなぜ両立しにくいのか」という問いから始まります。そして明治時代の読書文化から現代に至るまでの流れを丁寧に追いながら、各時代における働き方と読書習慣の関係性を分析しています。最終的には「今、私たちはどのように読書の時間を確保できるのか」という結論に導いてくれる構成になっています。
荻原:日本人の読書習慣の歴史的な変遷も含まれているんですね。それは興味深いです。
松本:そうなんです。特に印象的だったのは、明治時代など過去の日本人は今よりも忙しい生活を送っていたはずなのに、ちゃんと読書の時間を確保できていたという事実です。「忙しいから本が読めない」という現代人の言い訳が、実は成り立たないことを歴史的な視点から明らかにしています。
2. 「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」との出会い

荻原:この本を読み始めたきっかけについて教えてください。
松本:私自身、社会人になってから読書量が一気に減ってしまった経験があり、それについてずっと漠然とした課題意識を持っていました。この本は書店で平積みされていて、タイトルに惹かれて手に取ったんです。
著者が94年生まれということもあり、私と年齢が近いことも購入の決め手になりました。著者は元々、文学部に進学した「文学少女」で、社会人になって本が読めなくなった経験から、そのことに強い疑問を持ち、最終的に読書評論の仕事をするようになった方です。その経歴にも共感を覚えました。
荻原:なるほど。自分自身の課題と著者の経験が重なったことで、より深く内容に共感できたんですね。
松本:はい。この本は新書でありながら、読書のための方法論や読書文化についての考察が深く書かれています。同じ悩みを持つ同世代の著者が、自分の問題意識を深く掘り下げて書いた内容だったので、非常に親近感を持って読むことができました。
3. 現代の読書文化における「対極の入り口」

荻原:本書を読んで、特に印象に残ったポイントはありますか?
松本:最も印象に残ったのは、現代における「読書の入り口」についての考察です。最近はTikTokやテレビなどのメディアで本が紹介され、それをきっかけに読書を始める人が増えています。本来、じっくり時間をかけて読む小説と、短時間で情報が切り替わるTikTokのような媒体は対極にあるはずです。
しかし、本書ではそのような対極にある媒体から読書という世界への入り口が開かれることについて、これは現代ならではの現象ではなく、時代が変わっても読書の入り口が様々な形で存在してきたことを指摘しています。この視点は非常に新鮮でした。
荻原:確かに、入り口が違うというのは興味深い視点ですね。対極の媒体なのに、一方が他方の入り口になっているというのは。
松本:そうなんです。TikTokのような短時間で次々と情報が切り替わる媒体と、じっくり時間をかけて読む小説は性質が全く異なります。しかし、その対極にあるものが入り口となって、読書の世界に導かれるという現象が起きています。
この考え方に触れて、自分が普段どのように情報に接しているかを見つめ直すきっかけになりました。「短い時間で大量の情報を消費する」という現代的な習慣と、「一つの作品にじっくり向き合う」という読書の本質をどう両立させるかという問いが生まれました。
4. 「全身全霊」から「半身半分」へ

荻原:著者が一番伝えたかったメッセージはどのような部分だと思いますか?
松本:著者が最も強調していたのは「半身半分」という考え方です。かつての日本では「全身全霊」で働くことが美徳とされてきました。特に男性中心社会では、仕事に全てを捧げるという価値観が強かったです。
しかし本書では、「半身半分」で働くことの重要性を説いています。これは週3勤務や時短勤務といった働き方だけでなく、自分の時間やエネルギーを複数の場所に振り分けるという考え方です。仕事一辺倒ではなく、趣味や読書など自分の居場所を様々な場所に作ることで、より豊かな人生を送れるということです。
荻原:現代の働き方改革とも通じる視点ですね。「全身全霊」ではなく「半身半分」。
松本:そうですね。著者は「みんなが半分で働ける社会こそ、働きやすい社会につながる」と主張しています。全身全霊で働くのは過去のものだと。
また、現代人が読書をしない理由として、単に働きすぎという問題だけでなく、「ノイズ」の存在も指摘しています。昔は労働時間が長くても、ノイズのない静かな時間があったため読書ができていました。しかし現代は、テレビやスマホ、SNSなど様々な情報のノイズに囲まれているため、集中して読書する時間を確保することが難しくなっているのです。
荻原:確かに、電車に乗っていても思いますが、スマホを開いていない人を探す方が難しいですよね。常に何かしらの情報を消費している状態です。
松本:まさにその通りです。そのような状況の中で、読書という「静かな時間」「ノイズのない時間」を過ごすことが難しくなっています。だからこそ、「半身半分」で働きながら、自分なりに読書の時間を確保していく必要があるのです。
5. 「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」はどんな人におすすめ?

荻原:この本はどのような方におすすめですか?
松本:まずは「なぜ本が読めないのだろう」と思っている方全般にお勧めします。特に若い世代の方には響くところが多いと思います。本書は94年生まれの著者が書いているので、TikTokやSNSといった現代的なメディアへの言及も多く、若い世代にとって共感しやすい内容になっています。
また、この本の素晴らしいところは、単に「読書の時間を確保する方法」を提示するだけでなく、日本の読書文化の歴史を辿りながら、現代の問題の本質に迫っている点です。そのため、読書文化や働き方に関心のある方にも価値ある内容になっています。
荻原:なるほど。年齢問わず、自分が最近本を読めていないと少しでも感じている方は、読むと新たな視点が開けるかもしれませんね。
松本:はい。本書を読むことで、現代社会における読書の難しさへの理解が深まり、自分なりの解決策を考えるきっかけになると思います。
私自身、この本を読んで非常に納得しました。「半身半分」で働くことの大切さや、様々な場所に自分の居場所を作ることの重要性を再認識できました。以前は手当たり次第に解決策を探していましたが、この本を読んでからは道筋が見えてきた感じがします。
荻原:「全身全霊」をやめて「半身半分」で生きることの大切さが、今の日本社会では特に重要なメッセージかもしれませんね。日本語の「過労死」という言葉が世界中で使われるほど、働きすぎる文化があるわけですから。
松本:そうですね。働きすぎの文化を見直し、自分の人生を豊かにするために読書の時間を確保する。それが本書の大切なメッセージだと思います。ぜひ多くの方に読んでいただきたい一冊です。
荻原:松本さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。読書と仕事の関係性について、歴史的視点も含めた興味深い内容でした。私も読んでみたいと思います。
本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒なぜ働いていると本が読めなくなるのか
【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。
営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。
ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。
荻原エデル
社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。
趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。
松本 有加里
群馬県出身。
大学卒業後、人材派遣会社で営業→事務と経験し2024年9月からアルヴァスデザインに入社。
趣味はアニメ・映画鑑賞。世界で一番嫌いなものは虫。