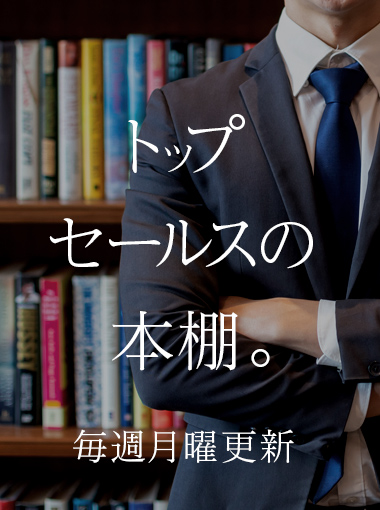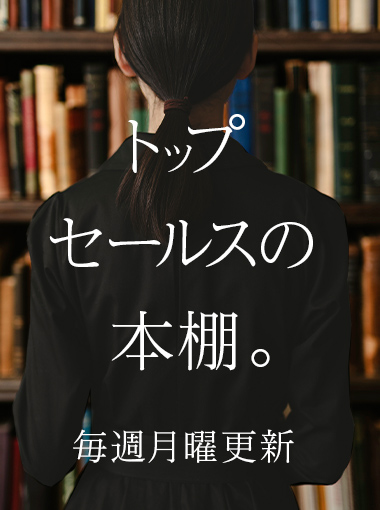プレイングマネージャーの「仕事の任せ方」大全(加藤定一著 2025年 三笠書房)後編~選択肢を絞り、相談を促すマネジメントの極意〜
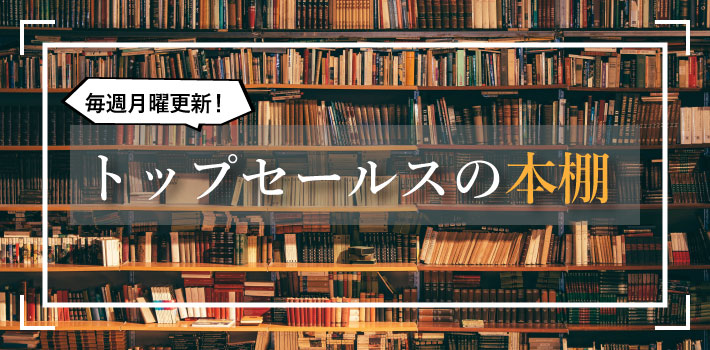
こんにちは。荻原です。
今回も引き続き、トップセールスの本棚をインタビュー形式でお届けしていきます。本日、インタビューに答えてくださったのは、プロデューサーとして活躍されている阿南さんです。
管理職として部下をマネジメントする際の実践的なノウハウが詰まった一冊として、加藤定一氏の『プレイングマネージャーの「仕事の任せ方」大全』をご紹介頂きました。

特に今回は、部下の成長を促進するマネジメントの核心について詳しくお話を伺います。
是非、ご一読ください。
目次
1. 「仕事の任せ方」が教える実践的マネジメント手法

荻原:本日は、よろしくお願いします。今回は前回に続き、5章から8章の内容について詳しくお聞きしたいと思います。まず、この部分の概要を教えていただけますか?
阿南:はい、ありがとうございます。5章から8章は以下のような構成になっています。
・5章「業務遂行状況を把握する」
・6章「業務遂行に介入する」
・7章「成果確認と評価面談の準備」
・8章「評価面談で育成する」
荻原:なるほど。業務の進捗把握から、必要な介入、そして評価面談という一連の流れで「部下の成長をどう支援し、どうフィードバックするか」が体系的に学べる構成なのですね。
2. 印象的だった「ジャムの法則」とは?

荻原:この中で特に印象に残ったエピソードはありますか?
阿南:はい、意思決定における「選択肢の数」が仕事の進め方に大きく影響するという点が非常に興味深かったです。
荻原:選択肢の数、ですか?
阿南:はい。「選択肢が多すぎると人は決められなくなる」という現象が、実はビジネスの現場でも頻繁に起きています。その例として紹介されていたのが、「ジャムの法則」という有名な実験です。
荻原:ジャムの法則とは、どんな実験だったのですか?
阿南:大学の教授がスーパーマーケットで、24種類のジャムが置いてある試食コーナーと6種類のジャムが置いてある試食コーナーを設けて、どちらがより多く購買に結びつくかを実験しました。
結果は、6種類のジャムコーナーの方が圧倒的に売れました。24種類置いてある試食コーナーは選択肢が多すぎて、購買意欲を減退させてしまったということです。
荻原:それは興味深い結果ですね。仕事の場面でも同じことが言えるということでしょうか?
阿南:はい。その通りです。何らかのアクションを行う際に、目の前の選択肢があまりにも多すぎると混乱して決定ができなくなってしまうのです。
そのため、マネージャーが部下に仕事を任せる時や状況確認をする時は、選択肢を絞った質問をする必要があるということです。
荻原:確かに、私たちも日々の仕事の中で、「どれをやるべきか迷う」ことってよくありますよね。
阿南:そうですね。だからこそ、「今、部下に選ばせようとしている選択肢は多すぎないか?」と、一度立ち止まってみることが大切かもしれません。
3. 具体的な期限設定の重要性

荻原:先ほど「選択肢を絞った質問をする」とありましたが、具体的には仕事を任せる際にどう活かせばよいのでしょうか?
阿南:例えば、期限を絞ることで選択肢を自然に限定できます。「3日以内」という条件がつけば、実行に時間がかかるものや効果が薄いもの、イメージが具体化されていないものなどの選択肢が排除されて、意思決定が容易になります。
荻原:つまり、しっかりとした条件を設けて仕事を依頼した方が、部下は動きやすいということですね。
阿南:まさにその通りです。これは私自身も実感していることで、仕事を誰かにお任せする時に、ざっくりと「これやっていただけませんか?」と内容だけお伝えすると、任せられた側は期限が設定されていなければ、どれくらいのものを作ればいいのか、作業工程をイメージしづらいのです。
荻原:確かにそうですね。具体例があれば教えてください。
阿南:例えば、「お客さまからいただいたこの内容を、スライド3枚にまとめてお客さんに提示したい。来週の火曜日までにいただけますか?」という聞き方をすると、受け取った側は「来週の火曜日まで」という条件から、今日は金曜日の午後だから手をつけられない、月曜日の午前中と火曜日の午前中でスライド3枚なら作れるかな、というふうに成果物をイメージしやすくなるという訳です。
荻原:なるほど。阿南さんご自身も、この部分を読んでから意識的に期限やゴール設定を明確にして仕事を依頼するようになったということですね。
阿南:はい、そうです。私自身も結構期限を設定せずに「いけますか?」「できますか?」みたいな質問を投げてしまうことがありました。その際の最初の返答が「できる・できない」ではなく「期限はいつですか?」「いつまでに提示すればよろしいですか?」と聞かれることが多いので、やはり言われた側もイメージしづらいのだなと実感しています。
4. 相談の重要性と主体的な相談の仕方

荻原:他にも印象に残った内容はありますか?
阿南:8章にあるコラム「もっと相談をしましょう」という箇所が印象的でした。報告・連絡・相談の中でも、特に相談についてもっと積極的に活用すべきだと書かれています。
荻原:相談について、どんなことが書かれているのでしょうか?
阿南:本来なら相談すべき場面があるはずなのに気づかないとか、課題発見力が不足している可能性があると指摘されています。そして、成長のためには相談が必要になるようなレベルの高い仕事を積極的に引き受けるべきだと書かれています。
荻原:確かに、管理職の立場だと、上司に相談するのは何となく好ましくないと思ってしまうこともありそうですね。
阿南:はい。自力で解決するのが美徳みたいに捉えられがちですが、適切な相談をすることでより良い判断ができるようになると書かれています。
そして、主体性のある相談の仕方として、「現状を伝えて分析した結果、解決策も合わせて自分の意見・判断を依頼する」という一連の流れで行うのが良いとされています。
荻原:具体的にはどのような効果があるのでしょうか?
阿南:上司からすると、そういう相談をされて何らかの答えを出すと、「ありがとうございます。参考になりました」と言われる。
著者の加藤さんも上司の経験が長く、部下から相談される機会が多い中で、そういうふうに相談されて答えを出してお礼を言われると、「役に立っている」という感覚になるそうです。
荻原:相談される側にとっても嬉しいことなのですね。
阿南:そうです。でも、もちろん上司を喜ばせるために相談しようということではなく、的確な相談がビジネスにおいて必要不可欠なスキルであるということです。
・相談したら迷惑をかける
・自分が未熟だから相談している
・相談したら評価が下がる
というのは誤解だと明記されています。
荻原:むしろ、相談が全く発生しないような仕事ばかりしているのは問題ということですか?
阿南:そうですね、必ずしも「相談がない=悪い」というわけではありませんが、本書では「相談が発生しない状態が続くのは少し注意が必要」とされています。
というのも、まったく相談せずに済んでいるということは、自分の持っているスキルや経験の範囲内で仕事を完結できているという可能性があります。
本来、成長に必要なのは、少し難しいことに取り組んでみること。その過程では必ず悩みや判断の迷いが生まれます。そうした時にこそ相談を通じて視野が広がったり、考えが深まったりしますよね。だからこそ、「相談が出るくらいのレベルの仕事」にこそ挑戦してほしい。そんなメッセージが込められていると感じました。
5. 新任マネージャーから経験豊富な管理職まで響く一冊
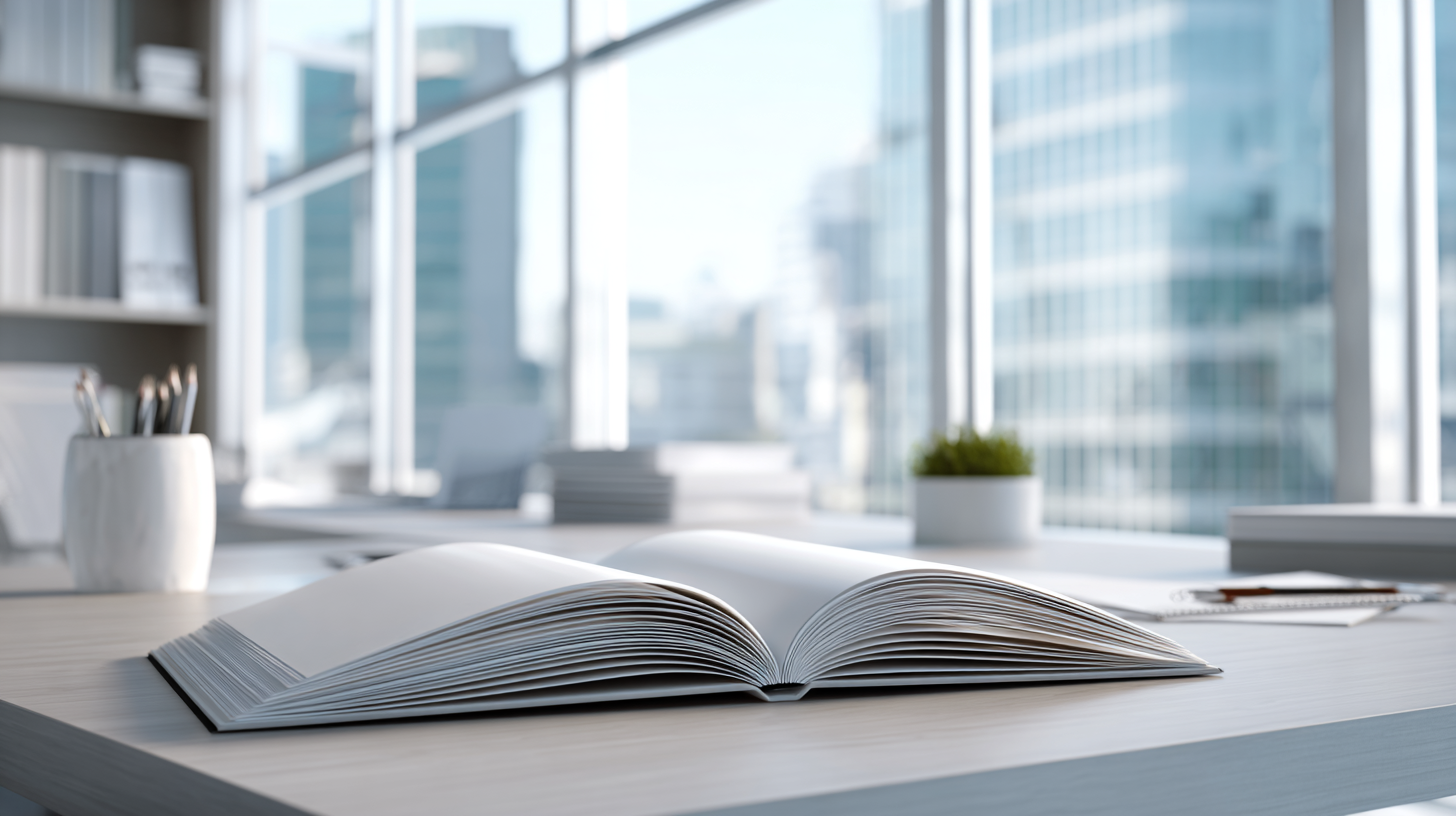
荻原:最後に、この書籍はどのような方におすすめでしょうか?
阿南:前半の1章から4章については、管理職の方でなくても、お互いに仕事を受け渡しするような職種の方であれば学びになると思います。
しかし、5章から8章の後半部分については、やはり部下の育成にフォーカスして重点的に解説されているので、後半になればなるほど部下がいる管理職の方向けだと思います。
荻原:著者の加藤定一さんご自身の経験についても触れられているそうですね。
阿南:はい。加藤定一さんご自身も長らく「マネージャーとは部下に正解を教えることが仕事だ」と思ってお仕事をされていたそうですが、キャリアの後半になって、部下と寄り添って個々の特性を活かすことの大切さに気づいたと書かれています。
教育者として正しいことを伝える視点と、伴奏者のように部下に寄り添う視点の両立を意識していただきたいとメッセージを送られています。
新任のマネージャーの方や、これからマネジメント業務に携わる方には、ぜひ早めにマインドセットのシフトを起こしていただけたらと思います。
荻原:本当に実践的で、すぐに活用できそうな内容が詰まった一冊ですね。「選択肢を絞る」「主体的な相談を促す」といった具体的な手法が、科学的根拠とともに説明されているのが印象的でした。
新任マネージャーの方はもちろん、既に管理職として活躍されている方にとっても、自身のマネジメントスタイルを見直すきっかけになりそうです。本日は貴重なお話をありがとうございました。
阿南:こちらこそ、ありがとうございました。
本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒プレイングマネジャーの「仕事の任せ方」大全
【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。
営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。
ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。
荻原エデル
社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。
趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。
阿南 康平
大学卒業後、システム開発を行うIT系ベンチャー企業に入社。個人事業主や中小企業の経営者に対しての新規開拓営業として、約2年従事。大手企業に対しての営業にチャレンジしたいという思いから、当社の理念に共感して2024年1月に入社。