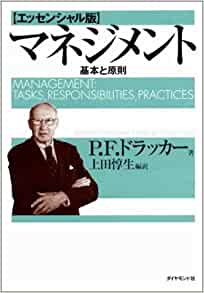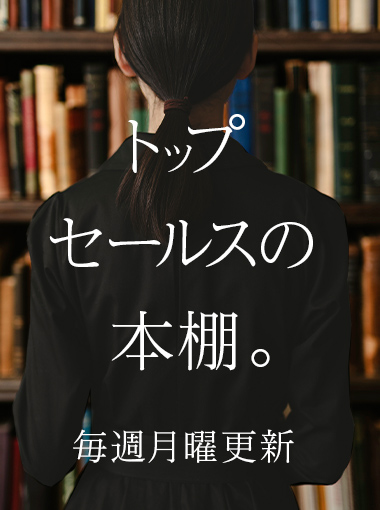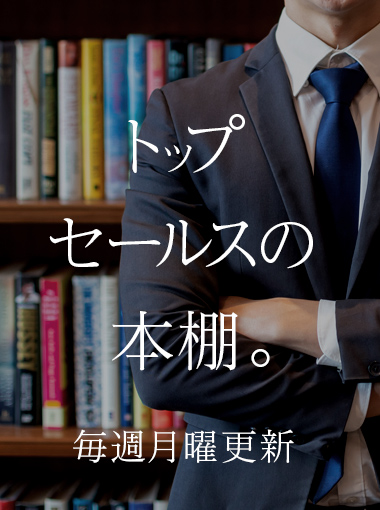【エッセンシャル版】マネジメント基本と原則⑪(ダイヤモンド社 2001年 P・F・ドラッカー著 上田惇生編訳)~自己管理をする上で大切なことは?~
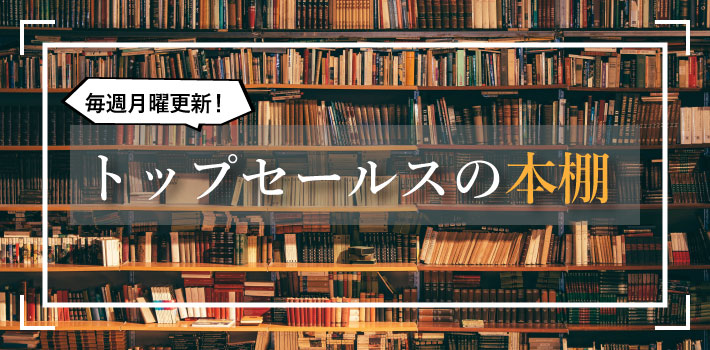
こんにちは、石井です。
これまで複数回にわたって、P・F・ドラッカーの「エッセンシャル版 マネジメント基本と原則」を取り上げています。
本日は11回目として、「マネジメントにおける自己管理」を考えていきます。
ドラッカーのマネジメントは、ややアカデミック性が高く、現場で応用するには一定の障壁があると考えられていることもあります。
そこで今回は、ドラッカースクールを卒業生である藤田勝利氏の著作「ドラッカースクールで学んだ本当のマネジメント(日経BP 2021年)」も参考にしながら読み解いきます。
第1回:マネジメントの基本と原則とは?
第2回:企業の目的とは?
第3回:戦略計画とは?
第4回:仕事の生産性とは?
第5回:仕事の働きがいとは?
第6回:マネジメントとチーム作りとは?
第7回:マネージャーの2つの役割とは?
第8回:マネージャーの5つの仕事とは?
第9回:マネジメント人材の開発とは?
第10回:目標管理をする上で大切なことは?
目次
1. マネジメントの目標管理(前回のあらすじ)

ドラッカーは、目標に関して3つの提言をしています。
- 目標は自らの率いる部門があげるべき成果を明らかにしなければならない。
- 他部門の目標達成の助けとなるべき貢献を明らかにしなければならない。
- 他部門に期待できる貢献を明らかにしなければならない。
目標について、多くの会社や組織で①を考える機会は多くあると思いますが、②や③に記載されているように他部門のことも考慮することが大切です。
また、目標をマネジメントする上で大切なことは「短期的視点」と「長期的な視点」を考慮することです。加えて、「量的なこと」だけではなく「質的なこと」も考慮して、目標をマネジメントしていく必要があります。
2. 自己管理の前に、目標管理ありき

今回お伝えする「自己管理」は、「目標管理」を密接に関連するため、前回のコラムをご覧でない方は、先にご覧いただくことをオススメします。(前回コラムへのリンク)
さて、ドラッカーが提唱する目標管理:Management by Objectiveを再度考えてみましょう。
Management by Objectiveは、目標管理と訳されていますが、注視すべきポイントは2つあると思っています。(※これらは、私の解釈によるものです。)
1つ目は、Managementという言葉です。
つまり、目標を「なんとかする」という意味があり、目標を「コントロール」するという意図はありません。
2つ目は、byという言葉です。
このbyには、「~によって」という意味があります。つまり、Management by Objectiveとは「目標によるマネジメント」という捉え方が適しています。
この2点を合わせると、マネージャーが保持すべき前提は「目標があることでマネジメントが機能する」ということだと思います。
3. 自己管理すると何が生まれる?
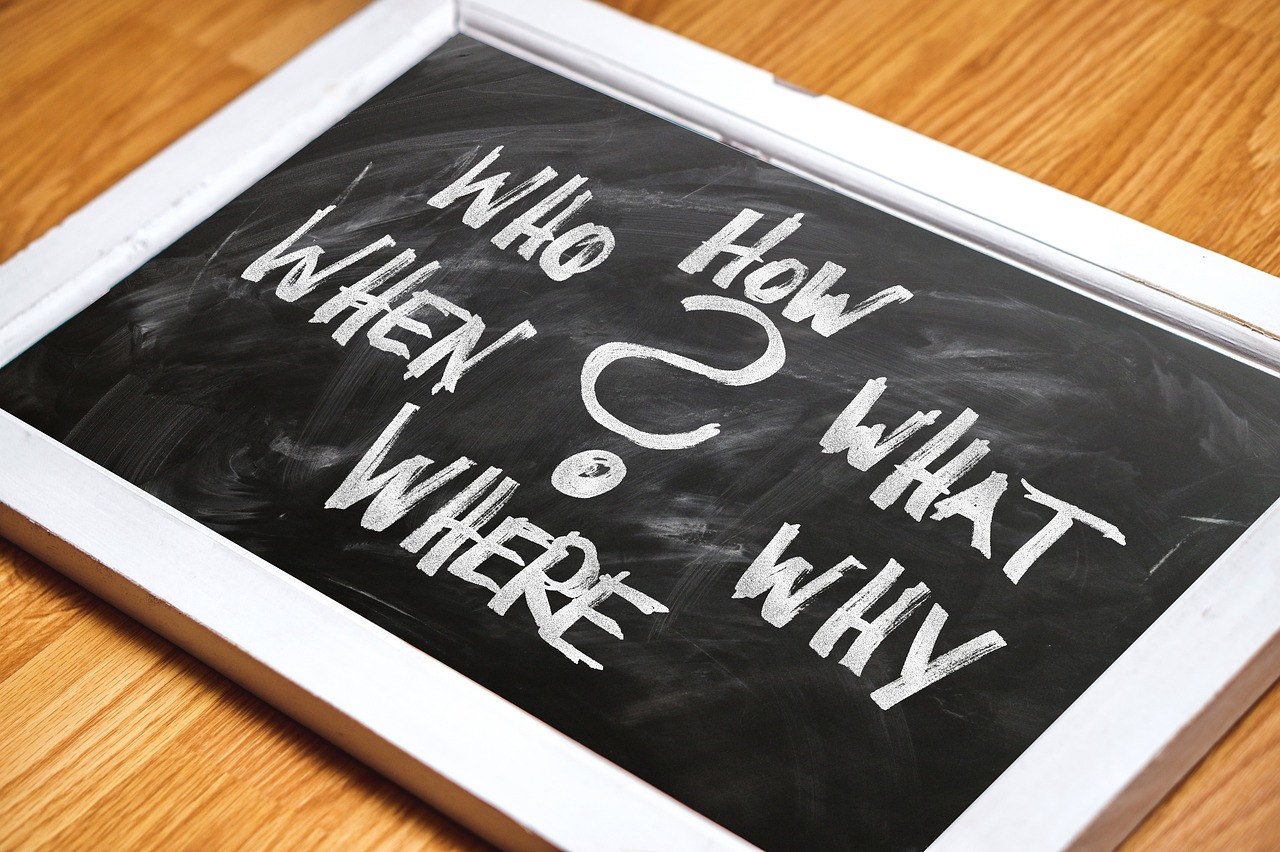
前述した通りに、目標によってマネジメントが活きている状態になった場合、私たちは何を手にすることができるでしょうか。
それは、「動機」だと思います。
言い換えれば、自らの仕事を目標によってマネジメントすることができれば、それは強い動機を生む結果になるのです。
ぜひ、皆さんも過去の仕事や、それ以外の活動でも構いませんので「ご自身が強く動機づけされた瞬間」を思い浮かべてみてください。
その中の1つには、「目標への想い」が強く、それによってマネジメントされた自分がいませんか?
これこそが、「目標管理」と「自己管理」をつなげる考え方ではないでしょうか。
4. 自己管理をする上で大切なことは?

ドラッカーは、自己管理についてこのような言葉を残しています。
自らの仕事ぶりを管理するには、自らの目標を知っているだけでは十分ではない。目標に照らして、自らの仕事ぶりと成果を評価できなければならない。
いかがでしょうか?ものすごく考えさせられる言葉です。
ここで前述した、目標管理をする上で大切な3つの観点を思い出しましょう。
>第九回:マネジメント人材の開発とは?
- 目標は自らの率いる部門があげるべき成果を明らかにしなければならない。
- 他部門の目標達成の助けとなるべき貢献を明らかにしなければならない。
- 他部門に期待できる貢献を明らかにしなければならない。
こちらです。ドラッカーは、仕事ぶりと成果を「自ら」評価しなければならないと述べています。つまり、②や③に記載されている他部門への貢献も、自分で評価しなければならないのです。
ドラッカーの目標管理は、とてもプロフェッショナルでハイレベルなことを要求していることを読み解くことができます。
では、他部門への貢献をどのように評価していけば良いのでしょうか。そこで大切になるのが、「情報」への向き合い方です。
5. 自己管理をする上での情報とは?

自己管理をする上で、情報を得ることは大切です。それはフィードバックによるものかもしれないですし、観察によって手に入れるものかもしれません。
ここで、ドラッカーが情報について記載しているメッセージを見てみましょう。
情報は、自己管理のための道具であって、上司が部下を管理するための道具ではない。
いかがでしょうか?多くの営業組織では、マネージャーが日々の業績数字を元に、目標を管理する光景が見て取れます。しかし、その多くは部下を管理するための行為になっていませんか?
正しい姿とは、その業績数字を使って部下が自らの目標を管理することです。上司はそのために何ができるかを考えるべきなのではないでしょうか。
6. おわりに

いかがでしたでしょうか?
本日は、ドラッカーのマネジメントの自己管理について考えてみました。
ドラッカーの目標管理と自己管理は、とても深みのある分野です。
前回と今回のコラムでは、私の個人的な解釈も多分に含んでいます。しかし、目標という言葉を見直し、管理という言葉を考え直すことで、日々の現場での仕事ぶりは変わってくるのではないでしょうか。
次回はミドルマネジメントを考えていきましょう。
>【エッセンシャル版】マネジメント基本と原則⑫(ダイヤモンド社 2001年 P・F・ドラッカー著 上田惇生編訳)~新種のミドルマネジメントとは?~
本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒【エッセンシャル版】マネジメント基本と原則(ダイヤモンド社 2001年 P・F・ドラッカー著 上田惇生編訳)
【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。
営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。
ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。
石井 健博
ブランドマネージャーとして、マーケティングを担当。
営業・リベラルアーツ・マネジメントなどのコラムを発信中。
趣味は、読書・英語学習・ラグビー。5歳息子のパパ。